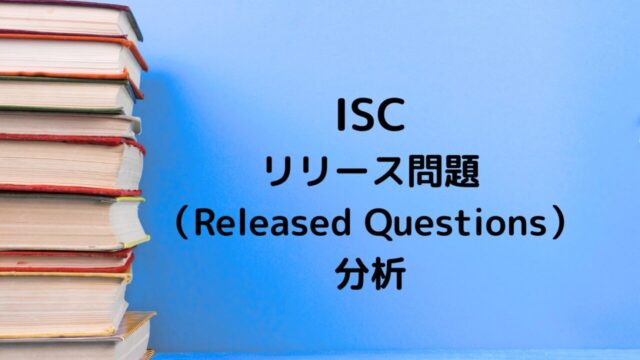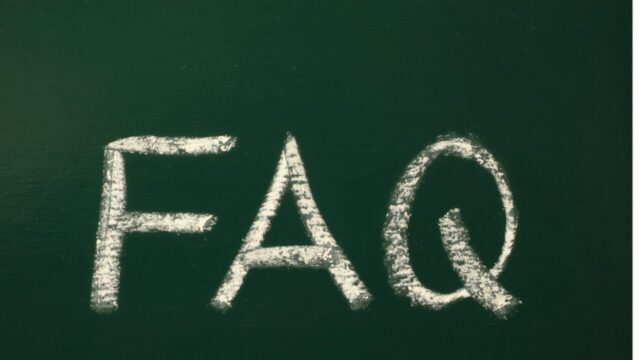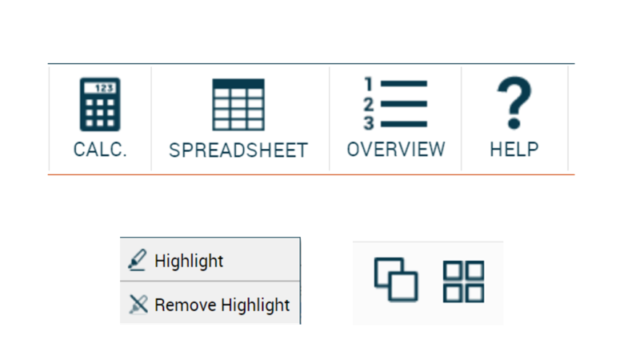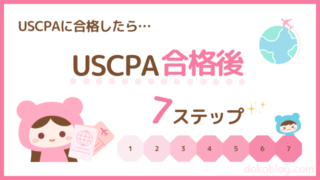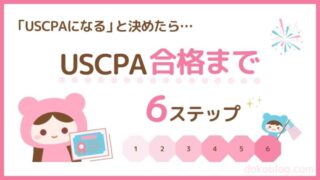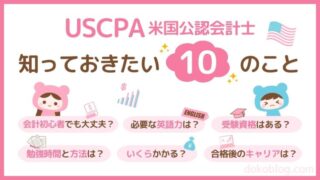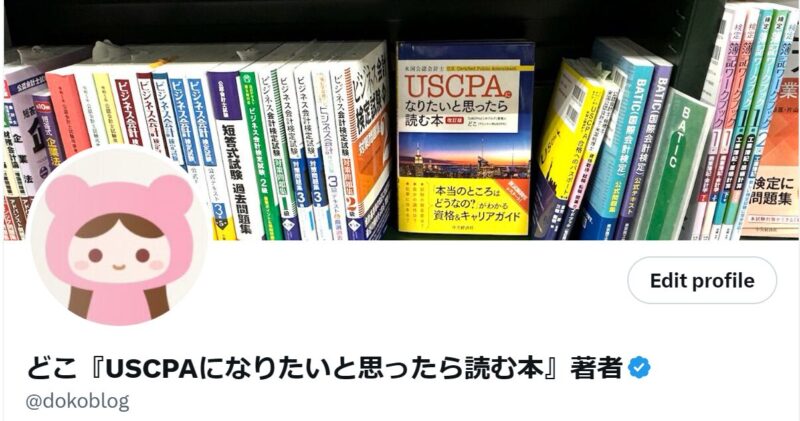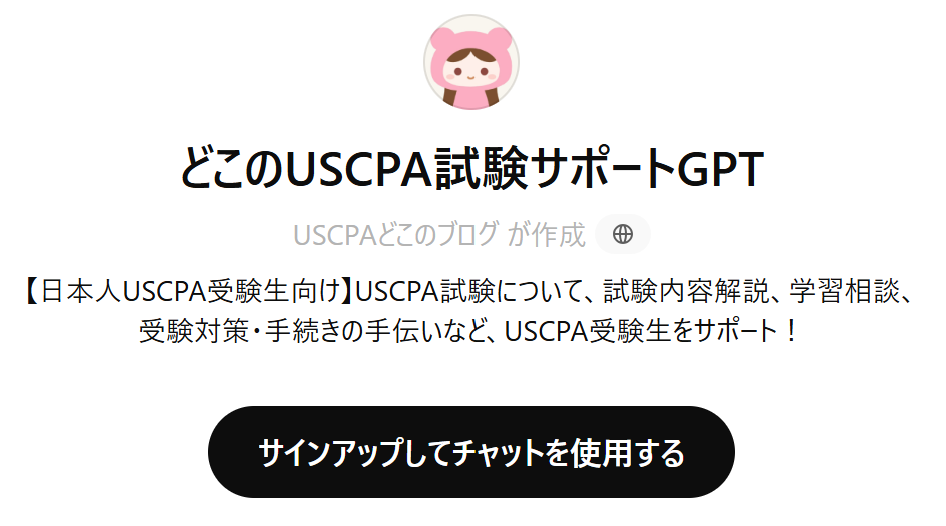【FAR】USCPAリリース問題(AICPA Released Questions)徹底解説
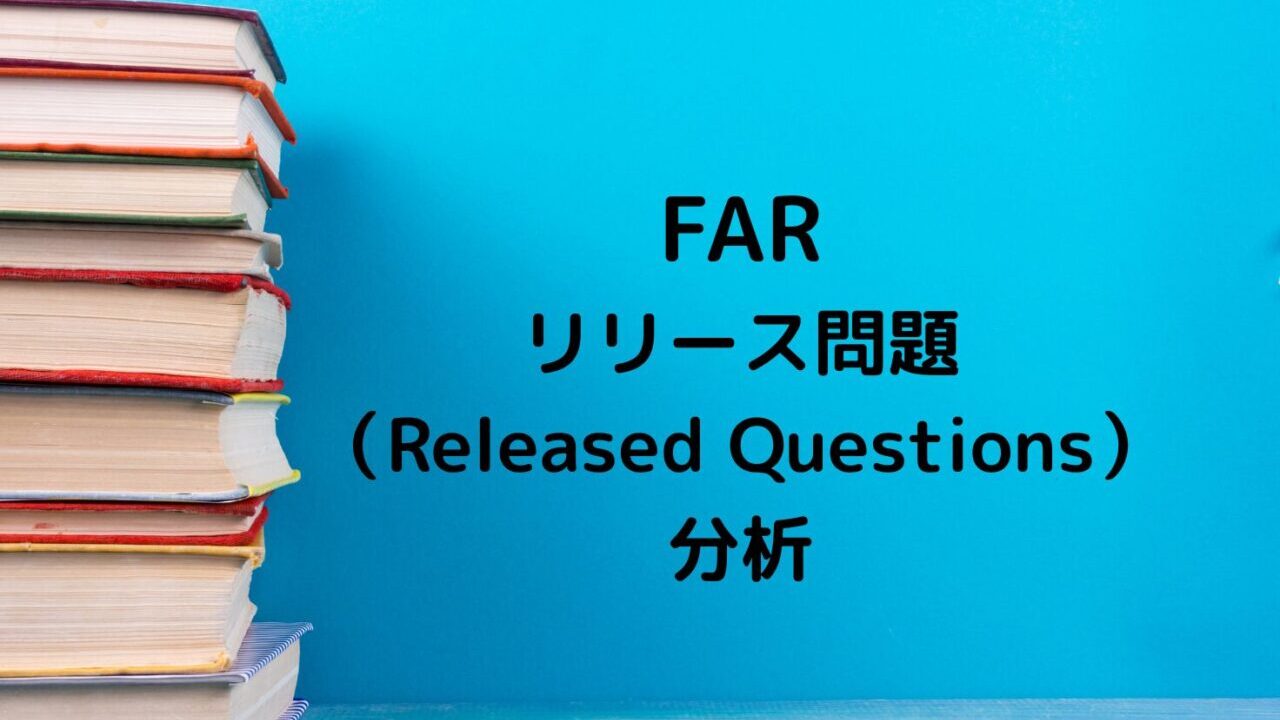

FARのリリース問題(AICPA Released Questions)をやっているけど、何が大事なのかあまりわからないよ。
誰かに解説してもらいたいな。

2019年から2025年までのFARのリリース問題を分析したよ。
どのようなトピックが大事なのか、どのように学習すればいいのか解説していくね。
まだUSCPA(米国公認会計士)に挑戦してない場合
USCPAは受験資格を満たすのにUSCPA予備校のサポートがマスト。
どこがおすすめするUSCPA予備校はアビタスです。
\無料・すぐ読める・オンライン参加可/
どこの著書『USCPA(米国公認会計士)になりたいと思ったら読む本』も参考にしてくださいね。
USCPA資格の活かしかた・USCPA短期合格のコツを書いています。
(2026/01/15 09:33:51時点 Amazon調べ-詳細)
- 注意:【FAR】USCPAリリース問題(AICPA Released Questions)解説にあたって
- 1.FARで特に重点を置くべきトピック
- (1)財務諸表の基本要素と表示
- (2)投資 (Investments)
- (3)キャッシュ・フロー計算書
- (4)収益認識 (Revenue Recognition) & リース (Leases)
- (5)公正価値測定 (Fair Value Measurement)
- (6)税効果会計 (Income Taxes)
- (7)連結会計 (Consolidations)
- (8)政府会計 (Governmental Accounting)
- (9)非営利組織会計 (Not-for-Profit Accounting)
- (10)SEC報告 (SEC Reporting)
- (11)1株当たり利益 (Earnings Per Share – EPS)
- 2.FARリリース問題の出題内容の分析
- 3.FARのリリース問題を基にした理解度チェック
- (1)財務諸表の構成要素と相互関係 (Financial Statement Elements & Relationships)
- (2)現金及び現金同等物 (Cash & Cash Equivalents)
- (3)棚卸資産 (Inventory)
- (4)有形固定資産 (Property, Plant, & Equipment)
- (5)無形資産 (Intangible Assets)
- (6)有価証券 (Securities)
- (7)負債 (Liabilities)
- (8)公正価値測定 (Fair Value Measurement)
- (9)非営利組織会計 (Not-for-Profit Accounting)
- (10)政府会計 (Governmental Accounting)
- (11)株式と株主資本 (Stock & Stockholders’ Equity)
- (12)税効果会計 (Income Taxes)
- (13)収益認識 (Revenue Recognition)
- (14)リース会計 (Leases)
- (15)後発事象 (Subsequent Events)
- (16)会計方針の変更と誤謬訂正 (Changes in Accounting Policies & Error Corrections)
- (17)連結財務諸表 (Consolidated Financial Statements)
- (18)その他の会計概念 (Other Accounting Concepts)
- 4.FARのリリース問題に出てくる理解すべき単語
- まとめ:FARのリリース問題で学習ポイントを押さえる
注意:【FAR】USCPAリリース問題(AICPA Released Questions)解説にあたって
FARのUSCPAリリース問題(AICPA Released Questions)の解説をしますが、少しフワッとした部分があるかもしれません。
リリース問題は、権利関係で誰でも入手できるものではありません。
なので、公に問題を1問1問、ネット上に書いていいものではありません。
あくまでも、過去のリリース問題を見て、どのような傾向があるか分析し、お伝えするのが精いっぱいとなります。
少しフワッとしているとしても、USCPA受験生にリリース問題を最大限に活かしていただくため、最大限の努力をしたと、ご理解いただければ幸いです。
当記事では、2019年から2025年までのFARのリリース問題を分析した結果に基づき、FAR受験生が、何をどのように学習したら良いか、解説していきます。
USCPA試験のリリース問題(AICPAリリース問題)については、こちらの記事が詳しいです。
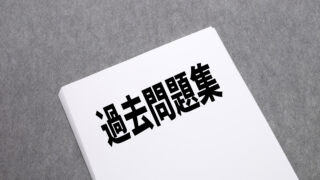
USCPA試験FAR受験対策を徹底解説!も参考にしてください。
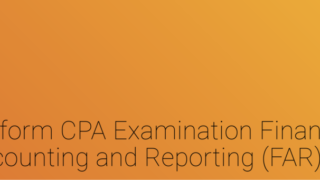
FARのリリース問題解説については、USCPAどこチャンネルの「【FAR】リリース問題(過去問)からの出題傾向解説」も参考にしてください。
TBS問題対策については、【TBS問題】USCPA試験 科目別TBS攻略法:具体的な対策と学習戦略を参考にしてください。
1.FARで特に重点を置くべきトピック
FARのリリース問題(2019年~2025年)を分析した結果、FARで特に重点を置いて学習すべきトピックが明確になっています。
リリース問題を通じて頻繁に出題されている、または、内容が複雑で深い理解が求められるトピックは以下の通りです。
これらを優先的に学習することで、効率的に得点アップを目指せると思いますよ。
注意:あくまでもリリース問題を分析した結果であり、「本番で出題される」または「本番で出題された」というわけではありません。
(1)財務諸表の基本要素と表示
資産、負債、資本の各勘定科目に関する計算問題や、取引が各財務諸表に与える影響を問う問題が豊富に出題されています。
➀ 現金及び現金同等物 (Cash & Cash Equivalents)
定義、含まれる項目、銀行残高調整、補償残高(Compensating Balance)、先日付小切手などの扱い。
➁棚卸資産 (Inventory)
移動平均法、ドル価値後入先出法(Dollar-Value LIFO)、先入先出法(FIFO)などの評価方法と計算、製造原価の構成要素、FOB条件による所有権移転、過年度の誤謬が財務諸表に与える影響。
③有形固定資産 (Property, Plant, & Equipment – PPE)
減価償却費の計算方法(定額法、二倍逓減法、級数法、半期換算法)、資産計上される利子コスト、非貨幣性資産の交換取引(商業的実態の有無)、減損損失の認識と測定。
➃株主持分 (Stockholders’ Equity)
株式発行、株式配当(低配当率の場合の会計処理と留保利益への影響)、現金配当の会計処理(決議日)、自己株式の消却、株式引受契約の不履行。
⑤負債 (Liabilities)
短期債務の借り換え、購入契約に関する負債認識、売上税の計算、新株予約権付社債の会計処理、実効金利法による利息費用のパターン、社債の発行価格計算、利払い日間の社債発行。
⑥偶発事象 (Contingencies)
偶発債務の認識基準(ProbableかつReasonably Estimable)、偶発利得の会計処理(実現時認識)、解雇給付金(Exit Costs)の負債認識。
⑦後発事象 (Subsequent Events)
財務諸表の修正が必要な事象と注記開示のみで良い事象の区別。
(2)投資 (Investments)
投資(Investments)も頻出トピックです。
➀持分証券 (Equity Securities)
評価方法(公正価値)、売却可能有価証券から売買目的有価証券への振替。
➁持分法 (Equity Method)
適用基準(20-50%の議決権保有、重大な影響力)、投資利益の計算、損失計上停止と利益計上再開の基準、投資残高の変動。
③債務証券 (Debt Securities)
売買目的(Trading)債務証券の評価、満期保有目的(Held-to-Maturity)債務証券の減損会計。
(3)キャッシュ・フロー計算書
特に間接法による営業活動によるキャッシュ・フローの調整計算や、投資活動・財務活動の区分に関する問題が頻繁に見られます。
(4)収益認識 (Revenue Recognition) & リース (Leases)
収益認識とリースは、BARでも出題されますね。
➀収益認識 (ASC 606)
5つのステップの理解、履行義務(Performance Obligation)の識別、契約の変更、収益認識のタイミング、契約費用(特にコミッション)の資産計上など、新しい収益認識基準に関する問題が定着しています。
➁リース (ASC 842)
リースの定義、リース開始日における負債の認識、リース料の構成要素、残価保証の扱いなど、リースに関する新しい基準の理解が求められます。
(5)公正価値測定 (Fair Value Measurement)
公正価値の定義、評価技法(市場アプローチ、収益アプローチ、コストアプローチ)、公正価値ヒエラルキーのレベル、主要な市場と最も有利な市場の概念など、公正価値に関する概念的な理解と適用が重視されています。
➀評価技法 (Valuation Techniques)
市場アプローチ、収益アプローチ、コストアプローチ。
➁インプットの階層 (Fair Value Hierarchy)
レベル1、レベル2、レベル3の区別とその具体例。
③市場の前提 (Market Premise)
主要な市場(Principal Market)と最も有利な市場(Most Advantageous Market)の区別と取引コストの扱い。
➃市場参加者 (Market Participants)
定義とその特徴。
⑤公正価値オプションの適用条件。
(6)税効果会計 (Income Taxes)
一時差異と永久差異の区別、繰延税金資産・負債の認識、評価性引当金の概念など、税効果会計の基本的な仕組みが問われています。
➀一時差異 (Temporary Differences)と永久差異 (Permanent Differences)
具体的な例とその違い。
➁繰延税金資産・負債 (Deferred Tax Asset/Liability)
認識と計算。
③評価性引当金 (Valuation Allowance)
認識。
➃未認識税務ベネフィット (Unrecognized Tax Benefit)
「More likely than not」の基準。
(7)連結会計 (Consolidations)
連結会計も押さえておくべきトピックです。
➀連結の要件(支配)と連結除外のケース
➁連結利益剰余金と連結純利益の計算
取得日時点での考慮
③非支配持分(Non-Controlling Interest)
表示。
(8)政府会計 (Governmental Accounting)
ファンド会計の分類、各ファンドに適用される会計認識基準(修正発生主義、発生主義)、政府全体財務諸表の特性などが定期的に出題されています。
➀ファンドの種類と会計基準
政府会計区分(Governmental Funds)(修正発生主義)、企業会計区分(Proprietary Funds)(発生主義)、受託会計区分(Fiduciary Funds)(発生主義)の理解。
➁各ファンドの目的と例
特別収入ファンド(Special Revenue Fund)、資本資産取得ファンド(Capital Projects Fund)、公営企業ファンド(Enterprise Fund)など。
③政府全体財務諸表(Government-Wide Financial Statements)
会計基準。
(9)非営利組織会計 (Not-for-Profit Accounting)
営利企業とは異なる会計処理や財務諸表の表示方法、特に活動計算書、正味資産の分類、寄付金収入の認識、費用の機能別分類などが繰り返し問われています。
➀財務諸表の種類と営利組織との類似点
活動計算書(Statement of Activities)が損益計算書に類似すること、財政状態計算書(Statement of Financial Position)における正味資産(Net Assets)の表示位置。
➁費用分類
プログラムサービス(Program Services)と支援サービス(Supporting Services)の区別、募金活動費用の認識。
③寄付金 (Contributions)
条件付き約束(Conditional Promises)の認識基準、複数年度にわたる誓約、交換取引部分の除外、現物寄付(法務サービス、消耗品)の認識。
➃正味資産の分類と再分類
寄付者からの使途制限のある正味資産(Net Assets with Donor Restrictions)と、理事会指定の準寄付基金(Quasi-Endowment)との区別、制限解除による再分類。
⑤コレクション(Collections)の会計処理。
⑥信託における受益者の持分(Beneficial Interest in Perpetual Trust)
評価。
⑦キャッシュ・フロー計算書(間接法)
利息の支払額の表示、代理取引(Agency Transactions)の表示。
(10)SEC報告 (SEC Reporting)
SEC報告も理解しておきましょう。
➀主要なフォーム (Form 8-K, 10-K, 10-Q)
目的と特徴、提出期限 (Accelerated Filerなど)。
➁要約財務諸表 (Condensed Financial Statements)
(11)1株当たり利益 (Earnings Per Share – EPS)
1株当たり利益も理解が必要なトピックです。
基本的1株当たり利益(Basic EPS)の計算
加重平均流通株式数(Weighted Average Number of Common Share Outstanding)の計算(株式発行、株式配当、自己株式の影響)。
2.FARリリース問題の出題内容の分析
FARリリース問題を2019年から2025年まで、どのような問題が出題されているのか分析しました。
(1)2019年のFARリリース問題分析
2019年のFARリリース問題は以下の通り。
➀財務諸表の変動分析と資本
キャッシュ、負債、その他の資産の変動に基づき株主資本の変動を計算する問題。期首資産・負債からの期末資本の計算。株式配当が資本に与える影響。
➁負債の分類
年次決算日後の長期借換えによる短期債務の非流動負債への分類と注記に関する問題。
③外貨建取引
期末の外貨建債務の換算レート(期末直物レート)に関する問題。
➃キャッシュ・フロー計算書
固定資産売却によるキャッシュの区分(投資活動)。
⑤非営利組織会計
支援サービス費用の分類(募金活動費)。
寄付された株式の評価(寄付日公正価値)。
⑥政府会計
特別収入ファンドと資本資産取得ファンドの会計認識基準(修正発生主義)。
⑦1株当たり利益(EPS)
基本的1株当たり利益の算定に使用する加重平均株式数。
⑧SEC報告
Form 8-K(重要な事象)、Form 10-K(年次)、Form 10-Q(四半期)、Form S-1(新規株式公開)の用途と、accelerated filerのForm 10-Q提出期限。
⑨現金及び現金同等物
構成要素の特定。
当座借越の表示(同じ銀行口座の残高との相殺)。
⑩棚卸資産
移動平均法による売上原価の計算。
製造業における棚卸資産の取得原価構成要素。
棚卸資産の購入契約(市場価格低下時の損失認識)。
⑪投資
売却可能有価証券から売買目的有価証券への振替時の未実現損益の認識。
⑫公正価値測定
評価技法(市場、収益、コストアプローチ)。
活発な市場における同一資産の相場価格の優先適用。
主要な市場がない場合の最も有利な市場の価格適用(取引コスト考慮前)。
⑬新株予約権付社債
新株予約権と社債への発行対価の配分(一方の公正価値が不明な場合)。
⑭減価償却
耐用年数変更時の減価償却費計算(定額法)。
⑮税務ベネフィット
認識すべきタックスベネフィットの金額決定(50%を超える可能性の閾値)
(2)2020年のFARリリース問題分析
2020年のFARリリース問題は以下の通り。
➀非継続事業
損益の計算(事業損益と処分損益を税引後で合算)。
➁キャッシュ・フロー計算書
間接法における営業活動と投資活動のキャッシュ・フロー計算。
③非営利組織会計
活動計算書での表示(募金活動の収益と費用は相殺不可)。
ユーティリティ事業を記録するファンド(公営企業ファンド)。
会員から受け取った寄付金の計算(サービス対価を除く)。
収益認識のタイミング(製品引き渡し時)。
➃SEC報告
Form 10-Kの提出期限(worldwide public floatによる区分)。
⑤現金主義会計
現金主義における損益の計算。
特別目的フレームワークに準拠した財務諸表の適切なタイトル。
⑥銀行勘定調整表
帳簿上の現金支払額の計算。
⑦棚卸資産
期末棚卸資産の計上額(F.O.B.条件と委託販売)。ドル価値後入先出法(dollar-value LIFO)による棚卸資産評価。
⑧減価償却
二倍逓減法による初年度の減価償却費。
⑨未払費用
有給休暇の費用計上(発生主義)。
⑩売上税
税込価格からの税抜商品価格と売上税額の計算。
⑪新株予約権付社債
新株予約権発行による株主資本の増加額。
⑫株式配当
株主資本勘定への影響(低配当率の場合)。
⑬偶発利得
利得の認識時期(実現時のみ)。
⑭繰延税金
税務上の減価償却費が会計上を上回る場合の繰延税金負債。
未認識税務ベネフィット(税務当局による否認可能性が高い場合)。
⑮公正価値測定
評価技法(類似証券の価格を用いる市場アプローチ)。
評価技法に使用するインプットの階層(類似資産はレベル2)。
最も有利な市場の価格(取引コスト考慮前)。
(3)2021年のFARリリース問題分析
2021年のFARリリース問題は以下の通り。
➀株主持分
株式発行、純利益、配当を考慮した期末の留保利益と株主持分残高の計算。
➁キャッシュ・フロー計算書
間接法における営業活動キャッシュ・フローの調整額(前払費用、買掛金、固定資産売却損)。
財務活動によるキャッシュ・フローの識別(借入金元本返済のみ)。
③非営利組織会計
活動計算書と営利企業の損益計算書の類似性。
特定目的信託基金ファンドの測定焦点と会計認識基準(経済的資源、発生主義)。
複数年度にわたる誓約の認識(初年度に割引現在価値、2年目以降は利息収益)。
偶発利得の計上(ゼロ)。
➃1株当たり利益(EPS)
株式発行、株式配当、自己株式取得を考慮した加重平均株式数の計算。
⑤現金主義会計
現金主義の利益計算。
現金受取額から発生主義収益への調整(期末契約負債の控除)。
⑥棚卸資産の誤謬
期末棚卸資産の過少計上が売上原価と純利益に与える影響。
⑦資産計上
建設・改修に係る利子コストの資産計上期間。
⑧非貨幣性資産の交換
商業的実態がない場合の利得認識額(受領した現金の割合)。
⑨持分法
持分法の適用範囲(議決権比率20%以上50%未満)。持分法による投資利益の計算。
⑩無形資産
特許権維持費用(法務費用)の会計処理(特許権勘定への借方計上と償却)。
⑪社債
実効金利法における社債割引発行時の支払利息の推移(毎年増加)。社債の発行価格計算。
⑫株式払込
株式引受契約の途中解約(追加払込資本の借方計上)。
⑬配当
現金配当の決議日における会計処理(留保利益の減額、未払配当金の計上)。
⑭繰延税金
繰延税金資産が生じる取引の例(前受金)。
⑮公正価値
市場参加者の定義(関連当事者ではない、知識がある、取引可能で意思がある者)。
(4)2022年のFARリリース問題分析
2022年のFARリリース問題は以下の通り。
➀包括利益
包括利益の計算(当期純利益とその他の包括利益の合計、税引後)。
➁連結会計
連結除外の要件(親会社が子会社に対する支配を失った場合、例:政府による厳しい制裁)。
③財務諸表の注記
会計方針の変更に関する注記の重複記載は不要であること。
➃非営利組織会計
条件付き約束の会計処理(条件達成時の認識、未収寄付金として計上)。
永久信託における受益者持分の評価(期末公正価値での再評価)。
寄付者による使途制限のある正味資産の増加額の計算(寄付基金、制限解除、準寄付基金の扱い)。
寄付されたサービスや消耗品の費用認識。公営企業ファンドの活動内容。
⑤売掛金
売掛金担保借入における売掛金勘定への仕訳(支配が譲渡人に残る場合は仕訳不要)。
⑥売買目的債務証券
貸借対照表上の表示額(期末公正価値)。
⑦無形資産
商標の耐用年数が無制限と判断されるケース(更新コストが低い場合)。
⑧負債
満期に普通株式を発行して償還する金融商品(負債として分類)。
⑨棚卸資産の誤謬
期首・期末棚卸資産の誤謬が売上原価に与える影響の修正計算。
⑩偶発債務
偶発債務の認識基準(損失の可能性が非常に高く、金額が合理的に見積もれる場合)。
⑪分割利息契約
分割利息契約の具体例(慈善信託剰余金)。
⑫収益認識
契約修正を別個の契約として扱う条件(独立した財やサービスの追加による範囲拡大)。
寄付金収入の報告額(無条件の約束と条件付き約束の扱い)。
⑬繰延税金:永久差異の例(税務当局への罰金)
未払法人所得税の計算。
⑭リース
残価保証の認識時期(リース開始日)。
⑮公正価値
減損テストにおける公正価値測定(主要な市場の価格、取引コストは考慮しない)。
(5)2023年のFARリリース問題分析
2023年のFARリリース問題は以下の通り。
➀キャッシュ・フロー計算書
現金増減額の計算(営業、投資、財務活動の各キャッシュ・フローを合算)。
➁連結会計
期中取得子会社の連結利益剰余金と連結純利益の計算。
子会社取得時の連結利益剰余金への影響(ゼロ)。
③非営利組織会計
寄付者による使途制限のある正味資産残高の計算(永久寄付基金と完了プロジェクトの扱い)。
固定資産合計額の計算(使途制限付き現金、固定資産、長期投資、建設目的の市場性有価証券、前払保険料の長期部分)。
正味資産の再分類の発生条件(寄付者が課した制限の解除)。
財務報告の正確な記述(支援活動はプログラムサービス以外の活動)。
利息支払額の表示(キャッシュ・フロー計算書の補足情報)。
➃政府会計
政府全体財務諸表に適用される会計認識基準(政府型活動、事業型活動ともに発生主義)。
⑤特別目的フレームワーク
修正現金主義会計に基づく財務諸表の適切なタイトル。
⑥現金及び現金同等物
構成要素の特定(当座預金、マネーマーケット、購入時点で満期まで3ヶ月以内の米国財務省短期証券)。
⑦棚卸資産
期末棚卸資産の評価額(定期棚卸制度、平均マークアップ率を使用)。
⑧利子コストの資産計上
建設に係る利子コストの加重平均利率の計算。
⑨減損損失
長期性資産の減損認識の要件(割引前将来キャッシュ・フローが簿価を下回る場合のみ)。
⑩減価償却
定額法と半期換算法を適用した減価償却費の計算。
⑪持分証券
売却益の計算(公正価値評価)。
持分法の適用条件(20%〜50%の議決権、または重大な影響力)。
持分法停止期間後の利益認識再開条件。
⑫無形資産
経済的便益の消費パターンが特定できない場合の償却方法(定額法)。
⑬撤退コスト
従業員解雇給付金の負債認識額(役務提供期間に応じた費用計上)。
⑭社債
利払い日間の社債発行時における受領現金(額面と割引に加えて経過利息を含む)。
⑮誤謬訂正
過年度の減価償却費過大計上による期首利益剰余金への影響(税効果考慮後)。
⑯収益認識
取引における履行義務の件数(機械の引渡し、保証、設置作業)。
⑰公正価値オプション(FVO)
適用条件(金融商品全体に適用、特定のリスクには不可)。
⑱リース
リース契約の定義に最も適切に合致する契約(特定の資産の使用を支配する権利)。
⑲後発事象
決算日後、財務諸表発行前の株式発行の表示方法(注記開示のみ)。
(6)2024年のFARリリース問題分析
2024年のFARリリース問題は以下の通り。
➀資産計上
会社設立費用(会計ソフトウェアは無形資産として償却、株式発行費用は払込対価の減額)。
➁純利益の計算
税引前継続事業利益と非継続事業利益(税引後)を合算した純利益の計算。
③投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動に区分される項目(工場資産の売却収入、設備購入支出)の特定と計算。
➃連結会計
子会社取得日における連結利益剰余金への影響(子会社の取得日時点の利益剰余金は親会社の利益剰余金に加算されない)。
⑤非営利組織会計
財政状態計算書における正味資産の表示場所(長期負債の後)。
機能別費用の分類(支援活動はプログラムサービス以外の全活動)。
キャッシュ・フロー計算書における現金の流れの分類(補助金受領、サービス対価、寄付金回収、従業員・サプライヤーへの支払いは営業活動)。
⑥1株当たり利益(EPS)
加重平均流通普通株式数の計算(追加発行、自己株式購入を考慮)。
⑦特別目的フレームワーク
修正現金主義会計が特別目的フレームワークに該当すること。
税法基準に基づく財務諸表の適切なタイトル。
⑧売掛金
債権購入時の仕訳(ファクタリング手数料、貸倒引当金の設定)。
残高試算表における売掛金勘定の表示額(貸倒引当金控除前)。
⑨棚卸資産
インフレ環境下で現金を最も保持するための棚卸資産評価方法(後入先出法 LIFO)。
先入先出法(FIFO)による売上原価の計算(定期棚卸制度)。
⑩減価償却
級数法による減価償却累計額の計算。
⑪持分証券
期末の持分証券の評価に係る仕訳(売買目的の場合、未実現損益を当期損益で認識)。
持分法適用会社の投資勘定残高の計算(損失と配当を考慮)。
⑫無形資産
非貨幣性資産の交換による無形資産の取得原価(現金、土地の公正価値、弁護士費用を合算)。
⑬配当
未払配当金を計上する時点(配当決議日)。
⑭誤謬訂正
過年度の誤謬が期首利益剰余金に与える調整額の計算(未計上ボーナス、受領済み公共料金払戻し)。
⑮偶発損失
一般的に財務諸表での認識が不要な偶発損失の例(脅かされたストライキ)。
認識が必要な偶発損失の例(係争中の訴訟)。
⑯収益認識
履行義務の例(顧客への独自のサービスの提供)。契約コストの資産計上(販売員へのコミッション)。
⑰繰延税金資産
評価性引当金を設定する必要がある場合(税務ベネフィットが実現しない証拠がある時)。永久差異ではない項目(貸倒引当金の変動)。
⑱公正価値測定
評価技法(市場、収益、コストアプローチの3つ)。
取引価格が公正価値を表さない場合(取引コストを含む場合)。
公正価値測定において不要なタスク(特定の市場参加者の特定)。
⑲リース
借手がリース負債を認識すべき契約条項(特定の資産の使用を支配する権利)。
リース分類における考慮事項(リース料に含まれない借手による残価保証)。
⑳後発事象
決算日後、財務諸表発行前の配当決議(負債として認識せず、注記開示のみ)。
(7)2025年のFARリリース問題分析
2025年のFARリリース問題は以下の通り。
➀留保利益
自己株式の償却目的取得、株式配当、純利益を考慮した留保利益の期末残高計算。
➁キャッシュ・フロー計算書
利息支払額の補足開示額の計算(支払総額から資産計上額を控除)。
③連結会計
非支配持分の表示方法(資本の部に親会社の資本項目と区別して表示)。
➃非営利組織会計
寄付された蒐集品の資産計上判断(売却目的か、展示・研究目的で条件を満たすか)。
募金活動費用(発生時に費用認識)。
代理取引(第三者のために資金を徴収・分配)のキャッシュ・フロー計算書上の表示(営業活動における純額)。
⑤政府会計
ファンドの分類(市役所建設は資本資産取得ファンド、警察車両購入は一般ファンド)。
⑥公開企業の財務報告
Form 10-Qに要約財務諸表が含まれること。
⑦現金及び現金同等物
期末残高の計算(現金、小口現金、マネーマーケットのうち制限のない部分、先日付小切手は含めない)。
⑧固定資産
土地の取得原価の計算(購入価格、手数料、未払税金、撤去費用からサルベージ収入を控除)。
⑨投資
売買目的債務証券の利息収入の計算(割引償却を考慮)。
満期保有目的債務証券の減損会計処理(信用損失費用と信用損失引当金)。
⑩無形資産
特許権の減損損失の計算(回収可能性テストと公正価値測定)。
⑪有給休暇
有給休暇に係る負債の金額計算(従業員数、日給、取得する可能性を考慮した月次計上)。
⑫会計上の誤謬
損益計算書に与える会計修正の正味影響額の計算(保険料の前払費用未計上、広告費の誤分類、給料の未払計上、水道光熱費の過大計上)。
3.FARのリリース問題を基にした理解度チェック
FARのリリース問題から、重要論点の理解度を確認していただくためにまとめました。
(1)財務諸表の構成要素と相互関係 (Financial Statement Elements & Relationships)
貸借対照表 (Statement of Financial Position/Balance Sheet): 資産、負債、資本(純資産)のバランスを示します。資産 = 負債 + 資本。
損益計算書 (Income Statement): 一定期間の収益と費用の結果としての純利益または純損失を示します。
包括利益計算書 (Statement of Comprehensive Income): 純利益にその他の包括利益(OCI)項目を加えたものです。OCIは、年金会計の調整、外貨換算調整、売却可能証券の未実現損益など、純利益には含まれないが資本に影響を与える項目です。
キャッシュフロー計算書 (Statement of Cash Flows): 営業活動、投資活動、財務活動の3つのセクションに分けて現金の流入と流出を示します。
営業活動 (Operating Activities): 事業の主要な収益を生み出す活動。間接法では純利益を起点に非現金項目や営業資産・負債の変動を調整します。
投資活動 (Investing Activities): 長期性資産(有形固定資産、投資有価証券など)の取得と処分に関連する活動。
財務活動 (Financing Activities): 負債と株主資本の項目(借入、返済、株式の発行、配当の支払いなど)に関連する活動。
株主資本変動計算書 (Statement of Changes in Stockholders’ Equity): 資本金、資本剰余金、利益剰余金、その他の包括利益累計額の期間中の変動を示します。
- 資産、負債、資本の増減が相互にどう影響するか。
- 純利益が利益剰余金にどう影響するか。
- キャッシュフロー計算書の間接法における営業活動の調整項目。
- その他の包括利益に分類される具体的な項目。
(2)現金及び現金同等物 (Cash & Cash Equivalents)
現金: 硬貨、紙幣、銀行預金(普通預金、当座預金)、小切手、郵便為替など。
現金同等物: 購入時点から満期まで3ヶ月以内であり、価値の変動が無視できるもの。例:米国財務省短期証券(Treasury Bills)、コマーシャルペーパー、短期金融市場投資信託(Money Market Fund)。
当座借越 (Bank Overdraft): 同じ銀行の他の口座に十分な残高がある場合は相殺表示が可能ですが、そうでない場合は流動負債として計上されます。
先日付小切手 (Post-dated Checks): 指定された日付まで換金できないため、現金同等物には含まれません。
補償残高契約 (Compensating Balance Arrangement): 資金使途が制限される部分の現金は、現金及び現金同等物から除外されます。
- 現金及び現金同等物に含まれる具体的な項目と含まれない項目。
- 銀行勘定調整表における未決済小切手や未達預金の扱い。
- 当座借越の表示方法。
(3)棚卸資産 (Inventory)
棚卸資産の取得原価: 製造業の場合、直接材料費、直接労務費、製造間接費が含まれます。広告宣伝費などの販売費及び一般管理費は含まれません。
所有権の移転:F.O.B. Shipping Point: 出荷時点で買手に所有権が移転します。
F.O.B. Destination: 目的地到着時に買手に所有権が移転します。
委託販売 (Consignment): 委託者(売主)が所有権を保持します。
棚卸資産評価方法 (Inventory Valuation Methods):移動平均法 (Moving-Average Method): 購入の都度、平均単価を計算し、販売時に最新の平均単価を適用します。
後入先出法 (Last In, First Out – LIFO): 最後に購入された商品から先に販売されたと仮定します。インフレ環境下では売上原価が最大になり、税金費用を抑える効果があります。
先入先出法 (First In, First Out – FIFO): 最初に購入された商品から先に販売されたと仮定します。
ドル価値後入先出法 (Dollar-Value LIFO): 物価水準の変動を考慮して棚卸資産の層を認識し、LIFOを適用します。
購入契約 (Purchase Commitment): 取り決めた購入価格が現在の時価より高い場合、差額を負債として認識します。
- 期末棚卸資産に含まれるべき項目と含まれない項目。
- 各評価方法(特に移動平均法、LIFO、FIFO)の計算方法とその経済的影響。
- インフレ環境下で税金費用を抑えるための棚卸資産評価方法。
- 購入契約における損失認識の条件。
(4)有形固定資産 (Property, Plant, & Equipment)
取得原価 (Acquisition Cost): 資産を使用可能な状態にするためにかかる全てのコストを含みます。土地の場合、不動産手数料、未払財産税、旧建物の撤去費用などが含まれますが、土地改良費は別途計上されます。
利子コストの資産計上 (Capitalized Interest): 自社使用目的で建設または製作される固定資産にかかる利子費用は、資産が意図された用途に使用できる状態になるまでの期間のみ資産計上可能です。
減価償却方法 (Depreciation Methods):定額法 (Straight-Line Method): 毎年一定額を償却します。
二倍逓減法 (Double-Declining Balance Method – DDB): 定額法の2倍の償却率を未償却残高に乗じて償却します。残存価額は考慮しませんが、簿価が残存価額を下回らないように調整します。
級数法 (Sum-of-the-Years’ Digits Method): 耐用年数の合計を分母とし、残存耐用年数を分子とする比率を未償却残高に乗じて償却します。
半期換算法 (Half-Year Convention): 取得日の時期に関わらず、初年度に半期分の償却を計上し、残りの償却は最終年度に行います。
減損損失 (Impairment Loss): 回収可能性テスト(undiscounted net cash flowsが簿価を下回るか)で減損の兆候が確認された場合、簿価と公正価値(割引後キャッシュフローの現在価値)の差額を損失として認識します。
非貨幣性資産の交換 (Nonmonetary Asset Exchange):商業的実態あり (Commercial Substance): 利得・損失を認識します。
商業的実態なし (Lack of Commercial Substance): 原則として利得は認識しません。ただし、現金を一部受領した場合は、利得のうち現金の占める割合のみ認識します。損失は常に認識します。
- 有形固定資産の取得原価に含めるべきコスト。
- 利子コストの資産計上期間。
- 各減価償却方法の計算と特徴。
- 減損損失の認識と測定のプロセス。
- 非貨幣性資産の交換における利得・損失の認識ルール。
(5)無形資産 (Intangible Assets)
無形資産の償却 (Amortization):耐用年数が確定している無形資産: 経済的便益の消費パターンに従って償却します。パターンを合理的に決定できない場合は定額法を使用します。
耐用年数が無制限の無形資産: 償却は行わず、定期的に減損テストを行います(例:商標、のれん)。権利の更新費用が非常に低い場合、耐用年数が無制限とみなされることがあります。
特許権の防衛費用: 特許権の将来の経済的便益を維持するために不可欠な費用として、特許権勘定に資産計上されます。
- 無形資産の償却要件と償却方法。
- 耐用年数が無制限と判断される条件。
- 特許権防衛費用の会計処理。
(6)有価証券 (Securities)
持分証券 (Equity Securities):持分比率20%未満(重大な影響力なし): 公正価値で評価し、未実現損益は原則として当期損益に認識します。
持分比率20%以上50%未満(重大な影響力あり): 持分法を適用します。投資利益は被投資会社の純利益に持分比率を乗じて計算し、配当は投資勘定を減額します。
持分比率50%超(支配): 連結財務諸表を作成します。
債務証券 (Debt Securities):満期保有目的 (Held-to-Maturity – HTM): 償却原価で計上します。減損の兆候がある場合、償却原価と公正価値(回収可能額)の差額を信用損失費用として認識し、信用損失引当金を計上します。
売買目的 (Trading): 公正価値で評価し、未実現損益は当期損益に認識します。利息収入は額面利息にディスカウント償却額を加算(プレミアム償却額を減算)して計算します。
売却可能 (Available-for-Sale – AFS): 公正価値で評価し、未実現損益はその他の包括利益(OCI)に認識します。
分類変更: 売却可能証券から売買目的証券への分類変更の場合、未実現損益(OCIに認識されていた部分)は直ちに当期損益に認識されます。
新株予約権付社債 (Bonds with Warrants): 社債と新株予約権が分離型の場合、それぞれの公正価値に基づいて発行価格を配分します。片方のみ公正価値が分かる場合は、分かる方を公正価値で計上し、残りをもう一方に割り当てます。新株予約権に割り当てられた金額は株主資本(追加払込資本)を増加させます。
- 持分証券の会計処理(公正価値評価、持分法、連結)の条件と特徴。
- 債務証券の分類(HTM、Trading、AFS)ごとの評価方法と損益認識。
- 新株予約権付社債の発行時の会計処理。
(7)負債 (Liabilities)
流動負債の長期負債への借り換え (Refinancing of Short-term Obligations): 貸借対照表日後、財務諸表公表日前に長期負債に借り換えられた短期債務は、非流動負債として分類されます。
外貨建取引 (Foreign Currency Transactions): 期末日時点で保有する外貨建債権・債務は期末日の直物レートで換算し、換算差額は当期損益に計上します。
売上税 (Sales Tax): 売上税込みの価格から税抜商品価格と売上税額を計算する。
有給休暇 (Vacation Pay): 休暇が付与された年度に費用と負債を計上します。
偶発債務 (Contingent Liabilities): 損失の可能性が「probable」(高い)かつ金額を「reasonably estimable」(合理的に見積もれる)場合、損失と負債を認識します。可能性が「reasonably possible」(中程度)の場合は注記開示、可能性が「remote」(低い)場合は開示不要です。訴訟関連の偶発損失が典型例です。
偶発利得 (Gain Contingencies): いかなる場合も財務諸表に計上されず、利得が「realized」(実現した)時点で認識されます。
撤退コスト (Exit Cost) / リストラクチャリング費用: 従業員への解雇給付金など、リストラに伴う費用は、役務提供の期間に応じて負債を認識します。
社債 (Bonds Payable):発行価格: 額面と利息の支払額を実効金利で現在価値に割引いた合計額。
実効金利法 (Effective Interest Method): 利息費用は期首簿価に実効利率を乗じて計算され、社債の簿価の変動に伴って変化します。ディスカウント発行の場合、利息費用は償還まで増加します。
利払い日間の発行: 発行時に買手から前回利払い日からの経過利息を受領し、次の利払い日に全額の利息を支払います。
担保付借入 (Secured Loan): 債権を担保に差し入れても、債権に対する支配を借主が保持している場合、債権の消滅は認識せず、通常の借入処理のみを行います。
金融商品 (Financial Instrument): 無条件に普通株式を発行して債務を履行する義務がある金融商品は、負債として計上されます。
リース負債 (Lease Liability): リース開始日において、リース料の現在価値として計上されます。借手が合理的に行使すると見込まれる購入オプションの行使価格や、残価保証額(probableな場合)も含まれます。
- 負債の分類(流動/非流動)の判断基準。
- 外貨建債務の期末換算ルール。
- 売上税の計算と会計処理。
- 有給休暇の費用認識タイミング。
- 偶発債務の認識要件と偶発利得の非認識ルール。
- 社債の評価(発行価格、実効金利法)。
- 担保付借入の会計処理。
- リース負債の計算に含まれる要素。
(8)公正価値測定 (Fair Value Measurement)
公正価値 (Fair Value): 測定日における市場参加者間で行われる秩序ある取引において、資産を売却して受け取る価格、または負債を移転して支払う価格。
評価技法 (Valuation Techniques):市場アプローチ (Market Approach): 同一または類似する資産/負債の市場価格や関連情報を使用。
収益アプローチ (Income Approach): 将来の利益やキャッシュフローの割引現在価値を算定。
コストアプローチ (Cost Approach): 代替資産の再調達原価を使用。
正味実現可能価額 (Net Realizable Value): 棚卸資産の低価法で用いられるが、公正価値測定には使用されない。
公正価値の階層 (Fair Value Hierarchy): 評価技法に使用するインプットの観察可能性に基づき、以下の3つのレベルに分類され、レベル1が最も優先されます。
レベル1: 活発な市場における同一の資産または負債の(未調整)相場価格。
レベル2: レベル1以外の直接的または間接的に観察可能なインプット(類似資産の相場価格など)。
レベル3: 観察不能なインプット。
市場の前提:主要な市場 (Principal Market): 取引量と活動レベルが最も大きい市場。
最も有利な市場 (Most Advantageous Market): 取引コスト控除後の受取額が最大となる市場(負債の場合は支払額が最小となる市場)。公正価値算定においては、取引コスト考慮前の価格を用います。
公正価値オプション (Fair Value Option – FVO): 特定の金融資産・負債について、公正価値で評価することを選択できる会計処理。金融商品ごとに適用され、特定のリスクに対してのみ適用することはできません。
- 公正価値測定の3つの評価技法。
- 公正価値の階層の定義と具体例。
- 主要な市場と最も有利な市場の区別、および取引コストの扱いの違い。
- 公正価値オプションの適用条件。
(9)非営利組織会計 (Not-for-Profit Accounting)
財務諸表:財政状態計算書 (Statement of Financial Position): 営利組織の貸借対照表に類似。純資産は「使途制限なしの純資産 (net assets without donor restrictions)」と「寄付者からの使途制限付き純資産 (net assets with donor restrictions)」に分類されます。
活動計算書 (Statement of Activities): 営利組織の損益計算書に類似。収益と費用を報告し、純資産の変動を示します。費用は「プログラムサービス (program service)」と「支援サービス (supporting service)」に機能分類されます。
キャッシュフロー計算書 (Statement of Cash Flows): 営利組織と同様に営業活動、投資活動、財務活動に分類されます。
費用分類:プログラムサービス: 組織の主要な目的を達成するための活動に関連する費用(例:プログラムディレクターの給与、教育用チラシの印刷費用)。
支援サービス: プログラムサービス以外の活動に関連する費用。これには経営管理活動 (management and general)、募金活動 (fund raising)、会員獲得活動 (membership development) が含まれます。
寄付 (Contributions):無条件の約束 (Unconditional Promises): 誓約を受けた年度に現在価値に割引いた金額で収益を認識します。翌年度以降は利息収益を計上します。
条件付き約束 (Conditional Promises): 特定の条件が満たされた場合にのみ収益を認識します。
現物寄付 (Donated Services/Supplies): 特定の条件を満たす場合、市場価値で収益と費用を計上します。
純資産の再分類 (Reclassification of Net Assets): 寄付者による目的制限や時間制限が満たされた場合、活動計算書において「net assets released from restrictions」として表示されます。
準基金 (Quasi-Endowment): 組織の理事会が内部的に指定した基金であり、寄付者からの制限がない純資産として扱われます。
コレクション (Collections): 特定の条件を満たす場合、資産計上は不要で注記開示のみで済みます。
- 非営利組織の3つの主要な財務諸表とその特徴。
- 費用の機能分類(プログラムサービス vs. 支援サービス)の具体例。
- 寄付の種類(無条件、条件付き、現物)ごとの収益認識ルール。
- 純資産の再分類が生じるタイミングと表示。
- 準基金と使途制限付き基金の違い。
(10)政府会計 (Governmental Accounting)
ファンド会計 (Fund Accounting):政府会計区分 (Governmental Funds): 修正発生主義 (modified accrual basis) を使用。例:一般ファンド (General Fund)、特別収入ファンド (Special Revenue Fund)、資本資産取得ファンド (Capital Projects Fund)。
企業会計区分 (Proprietary Funds): 発生主義 (accrual basis) を使用。例:公営企業ファンド (Enterprise Fund)、内部サービスファンド (Internal Service Fund)。
受託会計区分 (Fiduciary Funds): 発生主義 (accrual basis) を使用。例:特定目的信託基金ファンド (Private-Purpose Trust Funds)。
政府全体財務諸表 (Government-Wide Financial Statements): 政府型活動と事業型活動のどちらにおいても発生主義を使用します。
- 各ファンド区分の会計認識基準(修正発生主義 vs. 発生主義)。
- 各ファンドの具体例とその目的。
- 政府全体財務諸表で適用される会計認識基準。
(11)株式と株主資本 (Stock & Stockholders’ Equity)
株主資本の構成要素: 資本金 (common stock)、資本剰余金 (additional paid-in capital)、利益剰余金 (retained earnings)、その他の包括利益累計額。
株式発行費用: 株式発行により受け取った金額からの減額として処理され、資産計上はされません。
配当 (Dividends):現金配当: 配当決議日 (date of declaration) に利益剰余金を減額し、未払配当金 (dividends payable) を計上します。自己株式には配当はなされません。
株式配当 (Stock Dividends):低配当率 (Small Stock Dividends – 20-25%以下): 配当決議日の時価で利益剰余金を減少させます。
高配当率 (Large Stock Dividends – 20-25%以上): 額面価額で利益剰余金を減少させます。株式配当は資本項目内の振替であり、資本の総額には影響しません。
自己株式 (Treasury Stock):取得: 自己株式の取得目的(消却目的か、再発行目的か)により会計処理が異なります。消却目的の場合、取得と同時に消却の会計処理を行い、発行時に計上した払込資本を取り崩します。
再発行: 取得原価法または額面法で会計処理されます。
基本的1株当たり利益 (Basic Earnings Per Share – EPS): 普通株式1株当たり当期利益を示す指標。計算式の分母は加重平均流通株式数を用います。株式分割や株式配当は、発行時期に関わらず期首から流通していたとみなして計算します。
払込契約 (Subscription Basis): 株式の払込が途中で途絶した場合、一度計上した全ての会計処理を取り消す必要があります。
- 株式発行、配当、自己株式取引が株主資本の各項目に与える影響。
- 株式配当の低配当率と高配当率の会計処理の違い。
- 基本的EPSの計算における加重平均流通株式数の算出方法。
(12)税効果会計 (Income Taxes)
一時差異 (Temporary Differences): 財務会計と税務会計の収益・費用認識のタイミングの相違により生じる差異で、将来解消されるもの。
将来加算一時差異 (Taxable Temporary Differences): 将来、課税所得を増加させる差異。繰延税金負債 (deferred tax liability) を計上。例:税務上の減価償却費が会計上の減価償却費を上回る場合、割賦販売。
将来減算一時差異 (Deductible Temporary Differences): 将来、課税所得を減少させる差異。繰延税金資産 (deferred tax asset) を計上。例:前受金(会計上は収益ではないが、税務上は収益となる)、製品保証に係る引当金。
永久差異 (Permanent Differences): 財務会計と税務会計の規定の違いにより生じる差異で、将来解消されないもの。税金計算上は考慮されず、繰延税金資産・負債の計算には影響しません。例:罰金、地方債の受取利息、役員生命保険の保険料(会社が受取人の場合)。
評価性引当金 (Valuation Allowance): 繰延税金資産の税務上の便益が実現しない可能性が高い場合に設定されます。
未認識税務ベネフィット (Unrecognized Tax Benefit): 税務当局により否認される可能性が「more likely than not」(50%超)の場合、未認識税務ベネフィットを負債として計上し、税金費用を認識します。
- 一時差異と永久差異の区別と具体例。
- 繰延税金資産と繰延税金負債が発生する状況。
- 評価性引当金の設定条件。
- 未認識税務ベネフィットの認識条件。
(13)収益認識 (Revenue Recognition)
5つのステップ:顧客との契約を特定する。
履行義務を特定する。
取引価格を決定する。
取引価格を履行義務へ配分する。
履行義務を充足した時点で収益を認識する。
履行義務 (Performance Obligation): 売り手が顧客に商品やサービスを提供する契約上の義務。顧客への支配が移転した時点で充足されます。
契約変更 (Contract Modification): 契約の範囲が別個の財やサービスの追加により拡大された場合、別個の契約として処理します。
保証 (Warranty):法令等で要求される保証: 通常、別個の履行義務とはみなされず、発生した費用は製品保証費用として認識します。
顧客が別途購入する保証: 別個の履行義務とみなされ、収益として認識されます。
- 収益認識の5つのステップの理解。
- 履行義務が充足されるタイミング(例:商品が顧客に届けられた時点)。
- 契約変更の会計処理。
- 保証の種類の違いと収益認識への影響。
- 契約取得費用(例:販売手数料)の資産計上要件。
(14)リース会計 (Leases)
リースの定義: 一定期間にわたり、特定の資産を使用する権利を対価と引き換えに提供する契約。
リース負債の認識: リース開始日において、リース料の現在価値として計上されます。
リース料に含まれる要素: 固定リース料、借手が合理的に行使すると見込まれる購入オプションの行使価格、残価保証額(probableな場合)。
リースの分類 (Lessee):ファイナンスリース (Finance Lease): リース期間終了時に所有権が借手に移転する場合、購入オプションを借手が合理的に行使する場合、リース期間が経済的耐用年数の大部分を占める場合、リース料の現在価値が原資産の公正価値の大部分を占める場合、原資産が借手のみに専門化されている場合。
オペレーティングリース (Operating Lease): ファイナンスリースの条件を満たさないリース。
残価保証 (Residual Value Guarantee): リース終了時に原資産が一定額以上の価値を保持していることを借手(または第三者)が保証するもの。リース分類の判断基準の一つ。
- リースの定義とリース負債の認識タイミング。
- リース負債の計算に含まれる要素。
- リースの分類基準。
(15)後発事象 (Subsequent Events)
後発事象: 貸借対照表日より後だが、財務諸表の公表日または公表が可能となった日より前に起こった重要な事象。
認識が必要な後発事象 (Recognized Subsequent Events): 貸借対照表日時点で存在していた状況に関する追加情報を提供するもので、財務諸表の項目を修正します。例:取引先の倒産による貸倒れ、偶発債務の金額の確定。
開示が必要な後発事象 (Nonrecognized Subsequent Events): 貸借対照表日時点で存在していなかった状況に関するもので、財務諸表の項目は修正せず、注記開示のみを行います。例:社債や新株の発行、企業結合、異常な損失。
- 後発事象の定義と認識/開示の判断基準。
- 具体的な取引事例がどちらのタイプに該当するか。
(16)会計方針の変更と誤謬訂正 (Changes in Accounting Policies & Error Corrections)
会計方針の変更 (Changes in Accounting Policies): 会計処理原則の変更。原則として遡及適用し、財務諸表を修正します。注記に記載は一度でよい。
誤謬訂正 (Correction of an Error): 過去の財務諸表における間違いの修正。影響を受ける期首の利益剰余金を修正し、影響を受ける財務諸表項目を遡及的に修正します。
- 会計方針の変更と誤謬訂正の会計処理の違い。
- 誤謬訂正が利益剰余金に与える影響。
(17)連結財務諸表 (Consolidated Financial Statements)
連結の範囲: 親会社が子会社を支配(議決権の過半数所有)している場合、連結の範囲に含めます。
連結除外 (Deconsolidation): 子会社の支配を失った場合(例:政府や法廷の支配下に置かれる場合)に連結から除外します。
非支配持分 (Non-controlling Interest – NCI): 子会社の議決権のうち親会社以外の株主に帰属する部分。連結貸借対照表上、株主資本の部に親会社の資本項目と区別して表示されます。
連結利益剰余金と連結純利益: 親会社と子会社の利益を合算しますが、子会社の純利益は親会社に帰属する部分と非支配持分に帰属する部分に配分されます。子会社の利益剰余金は、親会社が子会社を取得した日からの増減のみが連結利益剰余金に影響します。
- 連結の条件と連結除外の条件。
- 非支配持分の表示方法。
- 連結利益剰余金と連結純利益の計算方法。
(18)その他の会計概念 (Other Accounting Concepts)
会計認識基準 (Basis of Accounting):発生主義 (Accrual Basis): 現金の受払に関わらず、経済事象が発生した時点で収益・費用を認識します。
現金主義 (Cash Basis): 現金の受払があった時点で収益・費用を認識します。
修正現金主義 (Modified Cash Basis): 現金主義と発生主義の要素を組み合わせた非GAAP会計処理。流動資産・負債は現金主義、長期性資産・負債は発生主義で計上します。
特別目的フレームワーク (Special Purpose Framework): GAAP以外の基準に準拠して作成された報告書(例:現金主義、税法基準)。
財務指標:総資産回転率 (Asset Turnover): 売上高 ÷ 総資産。資産の効率的な利用度合いを示す。
- 発生主義、現金主義、修正現金主義の基本的な違い。
- 特別目的フレームワークで作成された財務諸表のタイトル。
- 総資産回転率の計算方法。
4.FARのリリース問題に出てくる理解すべき単語
FARのリリース問題に出てくる単語で、理解しておくべきものをまとめておきます。
Accrual Basis (発生主義): 現金の受払に関わらず、経済事象が発生した時点で収益・費用を認識する会計基準。
Additional Paid-in Capital (資本剰余金): 株式の額面価額を超える金額で株式が発行された場合に生じる資本の一部。
Available-for-Sale Securities (売却可能有価証券): 公正価値で評価され、未実現損益がその他の包括利益(OCI)に認識される債務証券。
Balance Sheet (貸借対照表): 特定の時点における会社の資産、負債、株主資本を示す財務諸表。
Basic Earnings Per Share (基本的1株当たり利益): 普通株式1株当たり当期いくらの利益を獲得したかを示す指標。
Cash and Cash Equivalents (現金及び現金同等物): 手許現金、銀行預金、および購入日から満期までの期間が3ヶ月以内の流動性の高い短期投資。
Cash Basis (現金主義): 現金の受払があった時点でのみ収益・費用を認識する会計基準。
Capital Projects Fund (資本資産取得ファンド): 政府会計区分に属し、道路などの資本設備の取得や建設のために留保している資源の会計処理に使用されるファンド。
Commercial Substance (商業的実態): 非貨幣性資産の交換において、将来のキャッシュフローの規模、時期、リスクが大きく変化するかどうかを示す概念。
Comprehensive Income (包括利益): 当期純利益とその他の包括利益(OCI)の合計。
Conditional Promises (条件付き約束): 特定の条件が満たされた場合にのみ寄付が履行されるという約束。
Consolidated Financial Statements (連結財務諸表): 親会社と子会社の財務諸表を合算し、一つの経済実体として表示する財務諸表。
Contingencies (偶発事象): 将来に利益または損失を生む可能性を持つ不確実な事象。
Contingent Liabilities (偶発債務): 損失の可能性が「probable」かつ金額を「reasonably estimable」である場合に認識される負債。
Contributions (寄付): 非営利組織が受け取る無条件または条件付きの資金提供。
Cost Approach (コストアプローチ): 公正価値測定の評価技法の一つで、代替資産の再調達原価を用いる方法。
Deferred Tax Asset (繰延税金資産): 将来、課税所得を減少させ、税金費用を軽減する効果がある一時差異に基づいて計上される資産。
Deferred Tax Liability (繰延税金負債): 将来、課税所得を増加させ、税金費用を増加させる効果がある一時差異に基づいて計上される負債。
Depreciation (減価償却): 有形固定資産の取得原価を耐用年数にわたって費用配分するプロセス。
Discontinued Operations (非継続事業): 企業の主要な事業ラインまたは地理的事業域の処分または処分予定。損益計算書で税引後ベースで表示される。
Dollar-Value LIFO Method (ドル価値後入先出法): 物価水準の変動を考慮して棚卸資産の層を認識し、LIFOを適用する棚卸資産評価方法。
Double-Declining Balance Method (二倍逓減法): 定率法の減価償却方法の一つで、定額法の2倍の償却率を未償却残高に乗じて計算される。
Effective Interest Method (実効金利法): 社債の利息費用を期首簿価に実効利率を乗じて計算する方法。
Enterprise Fund (公営企業ファンド): 政府会計区分に属し、政府が住民に対するサービスを提供する事業型活動の会計処理に使用されるファンド。
Equity Method (持分法): 投資先企業に重大な影響力がある場合(通常、議決権比率20%以上50%未満)に適用される投資の会計処理方法。
Fair Value (公正価値): 測定日における市場参加者間で行われる秩序ある取引において、資産を売却して受け取る価格、または負債を移転して支払う価格。
Fair Value Hierarchy (公正価値の階層): 公正価値測定に使用されるインプットの観察可能性に基づいた3つのレベルの分類。
Fair Value Option (公正価値オプション): 特定の金融資産・負債について、公正価値で評価することを選択できる会計処理。
Financing Activities (財務活動): 現金の受払のうち、負債と株主資本の項目(借入、返済、株式の発行、配当の支払いなど)に関連する活動。
First In, First Out (FIFO) (先入先出法): 最初に購入された棚卸資産が先に販売されたと仮定する棚卸資産評価方法。
Foreign Currency Transaction (外貨建取引): 外貨で行われる取引。外貨建債権・債務は期末日に直物レートで換算される。
Fund Accounting (ファンド会計): 政府会計で用いられる、特定の目的のために資金が留保されている独立した会計単位。
Gain Contingencies (偶発利得): 将来利益を得る可能性のある偶発事象。会計上は実現するまで認識されない。
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) (一般に認められた会計原則): 米国で財務諸表を作成する際に準拠すべき会計基準の総称。
Governmental Funds (政府会計区分): 修正発生主義会計が適用される政府会計のファンド。
Government-Wide Financial Statements (政府全体財務諸表): 政府型活動と事業型活動の財務状況と業績を全体として示す財務諸表。発生主義が適用される。
Half-Year Convention (半期換算法): 取得日の時期に関わらず、初年度に半期分の減価償却を計上する減価償却の方法。
Held-to-Maturity (HTM) (満期保有目的): 満期まで保有する意図と能力がある債務証券。償却原価で計上される。
Impairment Loss (減損損失): 資産の回収可能価額が簿価を下回る場合に認識される損失。
Income Approach (収益アプローチ): 公正価値測定の評価技法の一つで、将来の利益やキャッシュフローの割引現在価値を算定する方法。
Income Statement (損益計算書): 一定期間の企業の収益と費用、およびその結果としての純利益または純損失を示す財務諸表。
Income Taxes Payable (未払法人所得税): 当期に発生した法人所得税のうち、まだ支払われていない金額。
Intangible Assets (無形資産): 物理的な実体を持たない識別可能な非貨幣性資産(例:特許、商標、のれん)。
Interest Capitalization (利子コストの資産計上): 特定の資産の建設・取得に関連して発生した利子費用を資産の取得原価に含めること。
Interim Financial Statements (期中財務諸表): 年次財務諸表より短い期間(四半期など)で作成される財務諸表。
Investing Activities (投資活動): 現金の受払のうち、長期性資産(有形固定資産、投資有価証券など)の取得と処分に関連する活動。
Last In, First Out (LIFO) (後入先出法): 最後に購入された棚卸資産が先に販売されたと仮定する棚卸資産評価方法。
Lease Liability (リース負債): リース契約に基づく将来のリース料支払い義務の現在価値。
Lessee (借手): リース契約において資産を使用する権利を得る側。
Long-lived Assets (長期性資産): 1年以上の期間にわたって使用される資産(有形固定資産、無形資産など)。
Market Approach (市場アプローチ): 公正価値測定の評価技法の一つで、同一または類似する資産/負債の市場価格や関連情報を用いる方法。
Market Participants (市場参加者): 公正価値測定における仮定上の取引の当事者で、知識があり、取引が可能で、取引の意思がある独立した当事者。
Measurement Focus (測定焦点): 政府会計において、ファンドの財務報告で何に焦点を当てるかを示す概念(例:現在の財務資源、すべての経済的資源)。
Modified Accrual Basis (修正発生主義): 政府会計区分で用いられる会計認識基準で、発生主義と現金主義の要素を組み合わせたもの。
Modified Cash Basis (修正現金主義): 現金主義に一部の発生主義的要素(例:長期性資産の減価償却)を加えた非GAAP会計基準。
Moving-Average Method (移動平均法): 棚卸資産を購入する都度、平均単価を計算し、販売時にその平均単価を適用する評価方法。
Net Assets (純資産): 非営利組織における資産から負債を差し引いた残額。
Net Assets Released from Restrictions (使途制限を外された純資産): 寄付者からの使途制限が満たされた際に、活動計算書で表示される純資産の再分類。
Net Assets with Donor Restrictions (寄付者からの使途制限付き純資産): 寄付者によって特定の目的や期間に利用が制限されている純資産。
Net Assets Without Donor Restrictions (使途制限なしの純資産): 寄付者からの使途制限がない純資産で、組織が自由に利用できる。
Non-controlling Interest (NCI) (非支配持分): 子会社の議決権のうち親会社以外の株主に帰属する部分。
Nonmonetary Asset (非貨幣性資産): 現金や固定された金額の債権・債務以外の資産(例:棚卸資産、固定資産、無形資産)。
Not-for-Profit Organization (非営利組織): 特定の受益者のために利益を追求しない組織。
Notes to Financial Statements (財務諸表の注記): 財務諸表の本体に含まれないが、理解に不可欠な追加情報を提供する部分。
Operating Activities (営業活動): 現金の受払のうち、事業の主要な収益を生み出す活動。
Permanent Differences (永久差異): 財務会計と税務会計の規定の違いにより生じる差異で、将来解消されないもの。繰延税金資産・負債の計算には影響しない。
Performance Obligation (履行義務): 売り手が顧客に商品やサービスを提供する契約上の義務。
Periodic Inventory System (棚卸計算法): 期末に実地棚卸を行い、売上原価と期末棚卸資産を計算する方法。
Pledges (誓約): 非営利組織への将来の寄付の約束。
Principal Market (主要な市場): 特定の資産または負債について、取引量と活動レベルが最も大きい市場。
Private-Purpose Trust Funds (特定目的信託基金ファンド): 受託会計区分に属し、個人からの遺贈などの財産を管理・記録するためのファンド。
Program Services (プログラムサービス): 非営利組織の主要な目的を達成するための活動。
Proprietary Funds (企業会計区分): 発生主義会計が適用される政府会計のファンド。
Purchase Commitment (購入契約): 将来一定の価額で一定の数量の棚卸資産を購入する契約。時価が高くなった場合に損失を認識する。
Quasi-Endowment (準基金): 非営利組織の理事会が内部的に指定した基金。寄付者からの制限がない純資産として扱われる。
Recoverability Test (回収可能性テスト): 減損の兆候がある長期性資産について、割引前将来キャッシュフローが簿価を上回るかどうかを判断するテスト。
Reclassification of Net Assets (純資産の再分類): 寄付者による目的制限や時間制限が満たされた際に、純資産の分類を変更すること。
Retained Earnings (利益剰余金): 会社の過去の利益の累積額から配当金を差し引いたもの。
Sales Tax (売上税): 米国において商品の販売時に課される税金。
Salvage Value (残存価額): 資産の耐用年数終了時の見積売却価額。
SEC (Securities and Exchange Commission) (米国証券取引委員会): 米国の証券市場を監督し、投資家保護のための情報開示を義務付ける政府機関。
Secured Loan (担保付借入): 資産を担保として提供して行われる借入。
Significant Influence (重大な影響力): 投資先企業の財務方針や経営方針に影響を与える能力(通常、議決権比率20%以上50%未満の場合に推定される)。
Special Purpose Framework (特別目的フレームワーク): GAAP以外の会計基準に準拠して作成された財務報告の総称。
Special Revenue Fund (特別収入ファンド): 政府会計区分に属し、特定目的のために使途制限されている収入の会計処理に使用されるファンド。
Split-Interest Arrangement (分割利息契約): 寄付者と信託などとの取り決めにより、収入が複数の受益者間で分配され、残りが慈善団体に寄付される契約。
Statement of Activities (活動計算書): 非営利組織の損益計算書に相当する財務諸表。
Statement of Cash Flows (キャッシュフロー計算書): 一定期間の現金の流入と流出を営業、投資、財務活動に分けて示す財務諸表。
Statement of Financial Position (財政状態計算書): 非営利組織の貸借対照表に相当する財務諸表。
Stock Dividends (株式配当): 会社が株主に追加の株式を無償で発行すること。
Straight-Line Method (定額法): 減価償却費を毎年一定額で計上する減価償却方法。
Subsequent Events (後発事象): 貸借対照表日より後だが財務諸表の公表日より前に起こった重要な事象。
Sum-of-the-Years’ Digits Method (級数法): 減価償却費が毎期一定額で逓減していく加速償却の方法。
Supporting Services (支援サービス): 非営利組織のプログラムサービス以外の活動に関連する費用(経営管理、募金活動など)。
Taxable Income (課税所得): 税法に基づいて計算される課税対象となる所得。
Temporary Differences (一時差異): 財務会計と税務会計の収益・費用認識のタイミングの相違により生じる差異で、将来解消されるもの。
Total Asset Turnover (総資産回転率): 売上高を総資産で割って計算される財務指標で、資産の効率性を示す。
Trading Securities (売買目的有価証券): 短期的な売買益を目的として保有される有価証券。公正価値で評価され、未実現損益は当期損益に認識される。
Treasury Stock (自己株式): 会社が自社の発行済み株式を買い戻し、再発行のために保有するもの。
Unconditional Promises (無条件の約束): 条件なしで寄付が履行されるという約束。
Unrecognized Tax Benefit (未認識税務ベネフィット): 税務当局により否認される可能性が「more likely than not」の場合に認識される負債。
Useful Life (耐用年数): 資産が使用されると見積もられる期間。
Valuation Allowance (評価性引当金): 繰延税金資産の税務上の便益が実現しない可能性が高い場合に設定される引当金。
Weighted-Average Number of Common Shares Outstanding (加重平均流通株式数): 特定期間における発行済み普通株式の平均数。EPSの計算に用いられる。
まとめ:FARのリリース問題で学習ポイントを押さえる
FAR試験では、基本的な仕訳や勘定残高の計算能力はもちろんのこと、概念的な理解と複雑な状況への適用能力が問われる傾向が強く見られます。
特に、NFP会計、政府会計、公正価値測定、繰延税金、収益認識、リース会計といった特殊な分野は、その独特なルールを正確に理解し、適用できるかが合否を分けます。
また、キャッシュ・フロー計算書に関する問題は非常に多岐にわたるため、徹底的な対策が必要ですね。
FAR試験は、財務会計の幅広い知識と深い理解が求められます。
単に暗記するだけでなく、概念をしっかりと理解し、具体的な計算や仕訳に落とし込める実践的な能力が重要です。
FAR学習の全体的なアプローチ
- 概念理解の徹底:なぜその会計処理が行われるのか、その背景にある会計基準の意図を理解することで、応用問題にも対応できるようになる。
- 計算問題の反復練習:多くの問題が計算を伴います。正確かつ迅速に計算できる能力を養うため、類似問題の反復練習が不可欠です。
- 仕訳の習得:貸借のバランスを理解し、取引が各勘定科目に与える影響を把握するために、主要な取引の仕訳を完璧に覚えることが重要です。
- 英語の会計用語の習得:試験は英語で行われるため、各会計概念に対応する正確な英語の用語を理解しておく必要があります。
リリース問題に基づいて学習法についてアドバイスをすると、このようになります。
FAR学習アドバイス
- 基礎固め:会計の基本原則(発生主義、企業会計の概念枠組み)を理解し、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書のつながりを意識して学習しましょう。
- 計算問題対策:各トピックの計算パターンを網羅的に学習し、実際に手を動かして問題を解く練習を繰り返してください。特に、減価償却費、棚卸資産の評価、社債の発行価格、EPSの計算、税効果会計、NFPの計算問題は頻出です。
- 概念と分類の理解:「なぜそうなるのか」「どこに表示されるのか」といった概念的な理解と、勘定科目の分類、キャッシュ・フロー計算書上の区分を正確に覚えることが重要です。特にNFP会計と政府会計は独特の概念が多く、集中的な学習が必要です。
- 最新会計基準の動向:収益認識(ASC 606)やリース(ASC 842)など、比較的新しい基準は詳細かつ頻繁に出題されます。これらの基準の原則、ステップ、および具体的な適用方法を深く理解しましょう。
- 誤謬訂正と包括利益:過年度の誤謬が利益剰余金に与える影響や、包括利益(Comprehensive Income)の計算は、複数の要素が絡むため注意が必要です。
- 英語の読解力:複雑な会計用語や専門的な文章に慣れるために、原文の解説を丁寧に読み込むことをおすすめします。
以上、6つののポイントを意識して学習することで、FAR試験の合格に近づけると思いますよ。
以上、「【FAR】USCPA試験リリース問題(AICPA Released Questions)徹底解説」でした。

重要論点は決まっているんだね。

ぜひ、この傾向に従って、FAR対策を進めて合格してね。
USCPA試験については、どこの著書『USCPA(米国公認会計士)になりたいと思ったら読む本』も参考にしてくださいね。
USCPA短期合格のコツも記載しています。
(2026/01/15 09:33:51時点 Amazon調べ-詳細)
まだUSCPAの勉強を始めていない場合は「USCPAの始めかた」も参考にしてください。