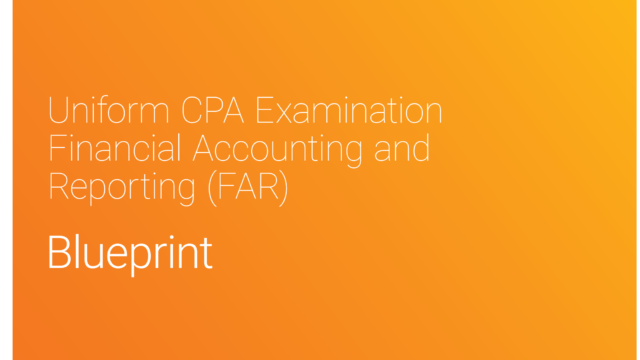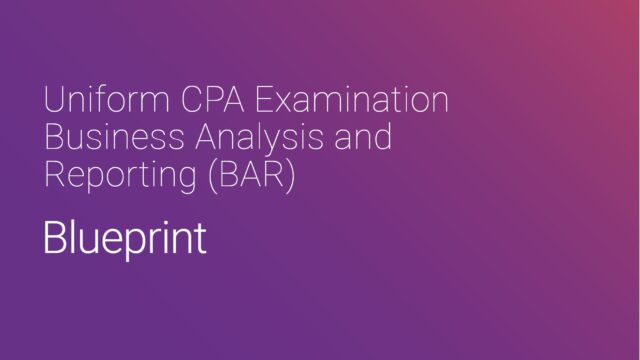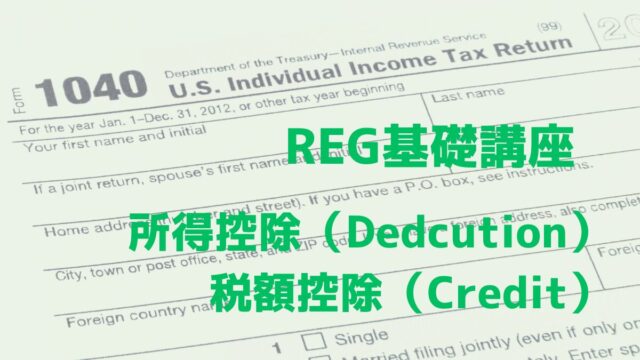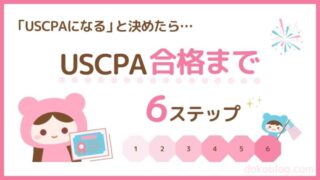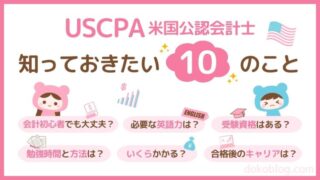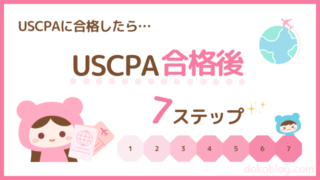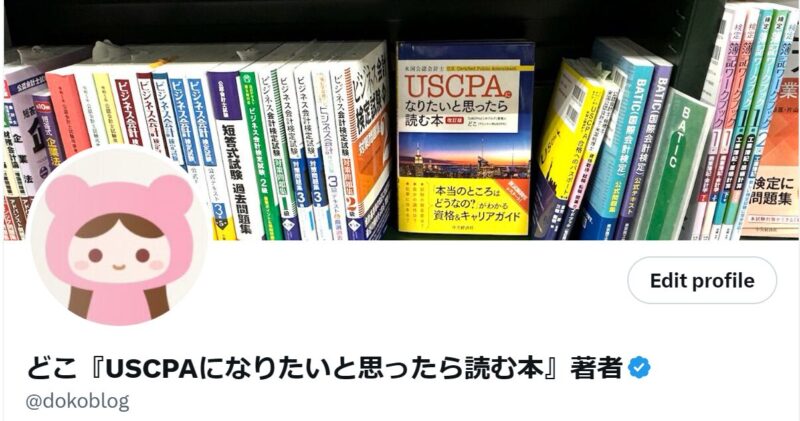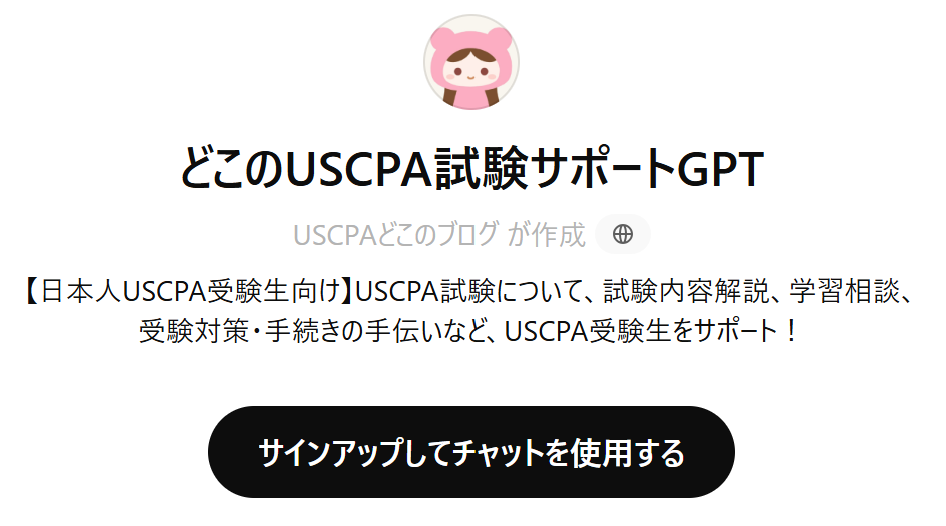【FAR基礎講座】収益認識(Revenue Recognition)ASC606 解説!USCPA受験生向け
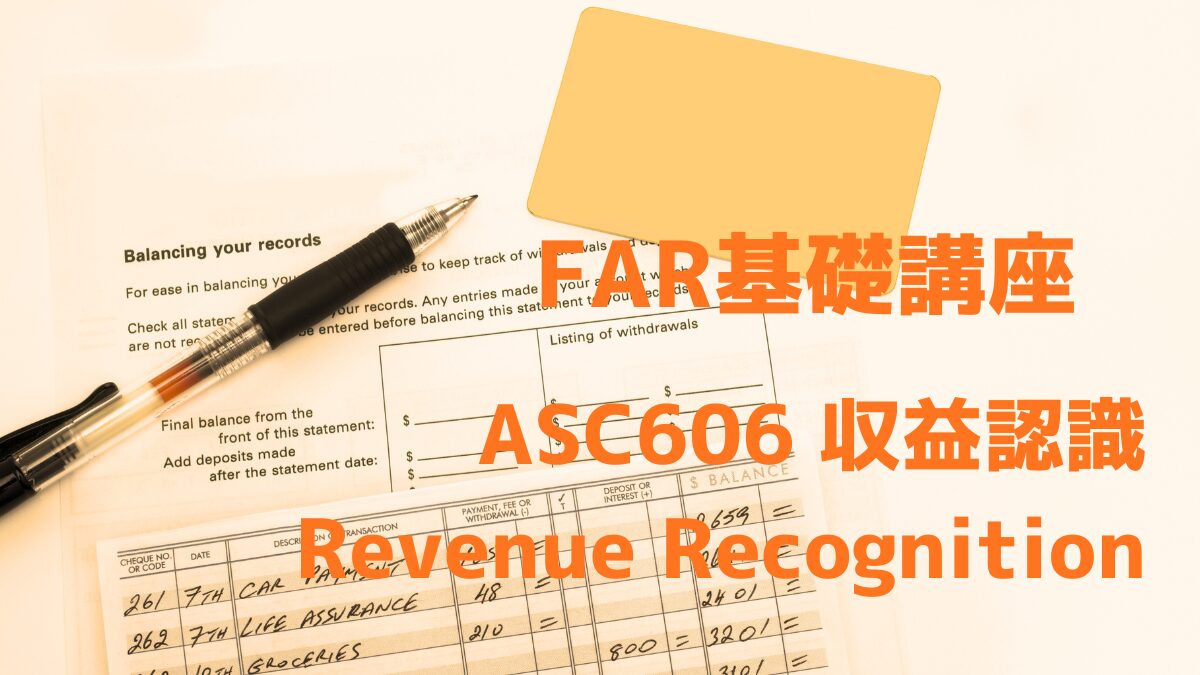

USCPA試験のFAR科目において、多くの受験生が苦手意識を持つ論点の一つが「収益認識(ASC 606)」だよ。
範囲が広く、一見複雑に見えるから、対策に苦労する受験生が少なくないんだよね。
この記事では、収益認識会計基準(ASC 606)の基本的な考え方から、試験で問われるMCQ(多肢選択式問題)やTBS(総合問題)の具体的な解き方までを網羅的に解説するよ。
この記事を読み終える頃には、収益認識が得意分野に変わっているはず。
一緒に完全攻略を目指そうね。
USCPA(米国公認会計士)は、受験資格を得るためにもUSCPA予備校のサポートが必要となります。
おすすめのUSCPA予備校はアビタスです!
日本のUSCPA合格者の約90%がアビタスで学習したんですよ(もちろん、どこもです)。
\無料・すぐに読める・オンライン参加可能/
どこの著書『USCPA(米国公認会計士)になりたいと思ったら読む本』も参考にしてくださいね。
USCPA資格の活かしかた・USCPA短期合格のコツを記載しています。
(2026/02/05 09:33:57時点 Amazon調べ-詳細)
もし音声で理解したい場合は、USCPAどこチャンネルの【FAR基礎】収益認識(Revenue Recognition)ASC606 解説 USCPA受験生向け をご覧ください。
また、以下の記事も参考にしていただけます。
USCPAのFAR勉強法のポイントとコツを解説!【最初からつまずかないために】

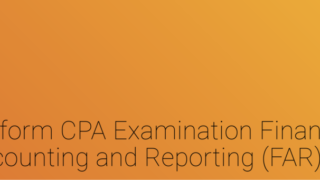
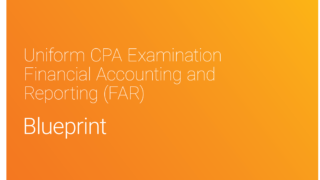
1. 収益認識会計基準(ASC 606)とは何か?
まず、ASC 606がどのような会計基準なのか、その全体像を理解することから始めましょう。
(1)なぜ新しい基準が必要だったのか?
ASC 606の正式名称は「顧客との契約からの収益(Revenue from Contracts with Customers)」です。
この基準は、米国の会計基準を設定するFASB(米国財務会計基準審議会)と、国際的な会計基準を設定するIASB(国際会計基準審議会)が共同で開発した「収斂(Converged)基準」として知られています。
そもそも、収益認識のルールはなぜ存在するのでしょうか。
端的に言えば、「企業が権利のない収益を計上することを防ぐため」です。
この基準が導入される以前、US GAAPには100を超える業界別の収益認識基準が存在していました。
これにより、業界が異なると同じような取引でも会計処理が異なるという問題が生じ、財務諸表の一貫性が損なわれ、企業間の比較可能性が低いという大きな課題がありました。
ASC 606は、この問題を解決し、グローバルで統一された単一のフレームワークを提供するために生まれました。
(2)収益認識の基本原則
US GAAPに基づく財務報告は、発生主義会計(accrual accounting)に基づいています。
現金主義(cash accounting)ではない点に注意してください。
ASC 606では、収益は「現金を受け取ったか」ではなく、契約上の履行義務をどの程度満たしたか(顧客への支配の移転)で認識します。
したがって、原則として現金受領は収益認識の条件ではありません。
収益認識は、(1)契約の識別→(2)履行義務の識別→(3)取引価格の決定→(4)配分→(5)履行義務の充足、という5ステップに基づいて判定します(時点認識/期間認識)。
ASC 606は、この「獲得」の概念をより精緻にしたものであり、契約から生じる企業の資産・負債の変化に基づいて収益を認識する「資産・負債アプローチ(Asset Liability Approach)」を採用しています。
これは、収益認識を契約上の権利(資産)と義務(負債)の変動として捉える考え方です。
2. 最重要フレームワーク!収益認識の5ステップモデル徹底解説
ASC 606の核心は、収益を認識するための5つのステップからなるモデルです。
FAR試験ではこのフレームワークの理解が絶対不可欠であり、最も重要な論点と言えます。
FARの試験では、この5ステップモデルを単に暗記するだけでなく、問題文のシナリオに「どのステップが問われているか」を瞬時に見抜く力が求められます。
各ステップの要点をしっかり押さえましょう。
この5ステップモデルは、まるで複雑なレストランの注文をさばくプロセスに例えることができます。
このイメージを頭に描きながら、各ステップを理解していきましょう。
収益認識の5ステップ
- 顧客との契約の特定
- 独立した履行義務の特定
- 取引価格の決定
- 履行義務への取引価格の配分
- 履行義務の充足時に収益を認識
ステップ1:顧客との契約の特定
ステップ1は、顧客との契約の特定 (Identify the contract with the customer)です。
【レストランの例え:注文の確認】
まず、お客様からの注文(契約)が有効で、代金を回収できる見込みがあるかを確認します。
収益認識は、顧客との有効な契約を特定することから始まります。
- 契約の定義: 契約とは、「強制力のある権利と義務を生み出す、二者以上の当事者間の合意」です。
- 契約の形態: 契約は書面である必要はなく、口頭や、商慣習から黙示的に成立するものも含まれます。
収益認識上、有効な契約とみなされるためには、以下の5つの基準をすべて満たす必要があります。
- 契約の承認と履行コミットメント: 両当事者が契約を承認し、それぞれの義務を履行することにコミットしていること。
- 各当事者の権利の特定: 移転される商品やサービスに関する各当事者の権利が明確に特定できること。
- 支払条件の特定: 提供される商品やサービスの支払条件が特定できること。
- 商業上の実質 (Commercial Substance): 取引が企業の将来のキャッシュフローに影響を与える、正当な事業上の理由があること。
- 対価の回収可能性が高いこと (Probable Collectibility): 企業が対価を回収できる可能性が高いこと。
この基準を満たさない場合、その取引はASC 606上の「契約」に該当しません。
したがって、収益は認識せず、受領済みの対価があれば負債(契約負債/前受金等)として計上します。
その後、次のいずれかを満たした時に限り、該当部分を収益化できます。
- 後日、契約要件(回収可能性を含む)を満たした
- 契約が終了した
- 企業に残存する履行義務がなく、移転済みの財・サービスに対応する対価が実質的に返金不要になった。
ステップ2:独立した履行義務の特定
ステップ2は、独立した履行義務の特定 (Identify the separate performance obligations)です。
【レストランの例え:個別の料理の特定】
次に、「コンボセット」の中にハンバーガー、ポテト、ドリンクという個別の履行義務(独立した料理)があることを確認します。
有効な契約を特定したら、次はその契約に含まれる企業の「約束」を特定します。
- 履行義務の定義: 履行義務とは、「顧客に明確な(distinct)商品またはサービスを移転する」という企業の約束です。
- 「明確(distinct)」の判断: 商品やサービスが「明確」であるとは、顧客がそれを単独で、または容易に入手可能な他の資源とともに便益を得られることを意味します。
単一の履行義務と複数の履行義務の例を挙げると次のようになります。
- 単一の履行義務の例: 注文住宅の建設契約では、基礎工事、配線、屋根工事など多くの作業が含まれますが、これらは単独では顧客に価値を提供しません。これらは高度に相互依存し、最終的に「家」という一つの製品に統合されるため、単一の履行義務として扱われます。
- 複数の履行義務の例: セキュリティシステムの設置と1年間の監視サービスをセットで販売する場合。設置と監視サービスはそれぞれが独立した価値を持ち、顧客はそれぞれから便益を得られるため、この契約には2つの履行義務が含まれます。
ステップ3:取引価格の決定
ステップ3は、取引価格の決定 (Determine the transaction price)です。
【レストランの例え:合計金額の決定】
注文したコンボの合計金額(変動する可能性のある割引やボーナスを考慮に入れる)を決定します。
契約に含まれる約束を特定したら、次は対価の総額を決定します。
取引価格とは、「企業が顧客から受け取ると期待する対価の額」です。
取引価格を決定する際には、以下の4つの要素を考慮する必要があります。
- 変動対価 (Variable Consideration) :将来の出来事(例:パフォーマンスボーナス、割引、返品)によって金額が変動する可能性のある対価です。推定方法として、期待値法(複数の成果が考えられる場合に、それぞれの確率で加重平均して見積もる方法)と最も可能性の高い金額法(成果が『ボーナス獲得』か『獲得できず』の二者択一である場合に、より可能性の高い方の金額を採用する方法)を用います。
- 重要な財務要素 (Significant Financing Component) :やサービスの移転と顧客による支払いのタイミングが大幅に(通常1年以上)ずれている場合、その取引には金利要素が含まれているとみなされます。この場合、取引価格は将来の受取額を現在価値に割り引いて測定します。
- 非現金対価 (Non-cash Consideration) :対価が現金以外(例:株式、不動産、他のサービス)で支払われる場合、その対価の公正価値(Fair Value)で取引価格を測定します。
- 顧客に支払われる対価 (Consideration Payable to the Customer) :企業が顧客に支払う割引、クーポン、リベートなどは、取引価格からの減額として扱います。
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ4は、履行義務への取引価格の配分 (Allocate the transaction price) です。
【レストランの例え:料理ごとの相対的な価格設定】
合計金額を、それぞれの料理(ハンバーガー、ポテト、ドリンク)の単品価格の比率(SSP)に基づいて配分します。
ステップ3で契約全体の取引価格が確定したところで、次の論理的なステップは、ステップ2で特定した個々の履行義務にその価格をどう配分するかです。
- 配分の原則: 取引価格は、各履行義務の相対的な独立販売価格(Relative Standalone Selling Price, SSP)の比率に基づいて配分されます。
- 独立販売価格(SSP): SSPとは、「その商品やサービスを個別に販売する場合の価格」です。
たとえば、ある会社がホームセキュリティシステムを販売しているとします。
システムの設置(SSP: $1,000)と1年間の監視サービス(SSP: 600)をセットで1,500で販売しました。
SSPの合計は1,600ですが、取引価格は1,500なので、100の割引があります。
この取引価格1,500は、各サービスのSSP比率($1,000 : $600)に応じて配分されます。
- 設置への配分額: 1,500×(1,000 / $1,600) = $937.50
- 監視サービスへの配分額: 1,500×(600 / $1,600) = $562.50
ハンバーガーセットのような単純な例でも、割引額が各商品のSSP比率に応じて比例配分されるという考え方は同じです。
ステップ5:履行義務の充足時に収益を認識
ステップ5は、履行義務の充足時に収益を認識 (Recognize revenue when or as the performance obligation is satisfied) です。
【レストランの例え:料理の提供と同時に認識】
そして、実際に料理(履行義務)を顧客に提供した時点(支配が移転した時点)で、配分された金額分の収益を認識します。ハンバーガーはすぐに、監視サービスは期間にわたって認識される、といった具合です。
最後のステップは、配分された収益をいつ認識するかを決定することです。
収益認識のタイミングは、企業が履行義務を充足し、顧客に資産の支配(control)を移転した時点です。
支配の移転を示す具体的な指標には、以下のようなものがあります。
- 企業が支払いを受ける現在の権利を有していること
- 顧客が資産の法的権利を有していること
- 顧客が資産の物理的占有を有していること
- 資産の所有に伴う重大なリスクと経済価値が顧客に移転していること
- 顧客が資産を検収したこと
認識のパターンには以下の2つがあります。
- 一時点での認識 (At a point in time) :小売店での商品販売のように、支配の移転が特定の瞬間に起こるケースです。上記セキュリティシステムの例では、設置完了時に$937.50の収益を一括で認識します。
- 期間にわたる認識 (Over time) :雑誌の年間購読サービスや長期の建設契約のように、企業が継続的に義務を履行し、顧客がその便益を享受するにつれて、収益を期間にわたって認識するケースです。上記セキュリティシステムの例では、監視サービスの$562.50を1年間にわたって月割りなどで認識します。
3. USCPA試験問題の解き方【論点別攻略法】
ここでは、MC問題とTBS問題の具体的な解き方を、頻出論点に基づいて解説します。
(1)MC問題対策:頻出パターンの理解
MCQでは、特定のシナリオにおける会計処理の正誤を問う問題が頻繁に出題されます。
➀繰延収益(Deferred/Unearned Revenue)
たとえば、繰延収益に関する問題の場合。
シナリオとしては、ギフト券の販売、雑誌の年間購読料の前受けなど。
会計処理のポイントは以下の通り。
- 現金を受領した時点では、まだ履行義務を充足していないため、収益は認識できません。この時点では負債(Unearned Revenue)として計上します。
- 顧客がギフト券を商品と交換した時点や、購読期間が経過した時点で履行義務が充足されるため、負債を減額し、収益を認識します。
- ギフト券が使用されずに失効(lapse)した場合も、企業は返金義務がなくなるため、その時点で収益を認識します。
仕訳は、「借方:Unearned Revenue / 貸方:Revenue」ですね。
➁長期建設契約
また、完成までに複数年を要する建設プロジェクトの場合。
会計処理のポイントは以下の通り。
- 通常、進捗度に基づいて収益を認識します(期間にわたる認識)。進捗度は (発生したコスト ÷ 総見積コスト) で計算されることが一般的です。
- 認識された収益(=現在までの発生原価+現在までの認識済総利益)が出来高請求額を上回る場合、差額は流動資産(Contract Asset)として計上されます。認識済総利益は (総見積総利益 × 進捗度) で計算します。
- (Costs incurred to date + Recognized Gross Profit to date) > Billings → Contract Asset
- 出来高請求額が認識された収益を上回る場合、差額は流動負債(Contract Liability)として計上されます。
- Billings > (Costs incurred to date + Recognized Gross Profit to date) → Contract Liability
(2)TBS問題対策:5ステップモデルを適用する思考プロセス
TBS問題では、与えられた資料(契約書など)を読み解き、5ステップモデルを適用して収益額や仕訳を導き出す能力が問われます。
➀TBS問題を解くために覚えるべきこと
TBS問題を解くために覚えるべきことは以下の通りです。
- 収益認識の5ステップモデルそのもの
- 繰延収益(Unearned Revenue)の会計処理と仕訳パターン
- 複数履行義務がある場合の取引価格の配分方法(相対的独立販売価格法)
- 長期建設契約の資産・負債の計算式
➁TBS問題の解き方ステップ
TBS問題の解き方のステップは以下の通り。
- 契約内容の把握: まず、問題文と添付資料(Exhibits)を注意深く読み、どのような取引が行われているのか全体像を理解します。
- 5ステップモデルの適用: 次に、頭の中で5ステップを順番に適用していきます。
ステップ1&2: 契約は有効か?契約に含まれる履行義務は一つか、複数か?を判断します。
ステップ3&4: 取引価格はいくらか?変動対価などの要素はあるか?複数の履行義務があれば、独立販売価格(SSP)を基に取引価格を配分計算します。
ステップ5: 各履行義務が「一時点」で充足されるのか、「期間にわたる」のかを判断し、最終的な収益認識のタイミングと金額を決定します。 - 仕訳または計算: 問題で求められている仕訳や数値を具体的に計算し、解答欄に記入します。
③間違えやすい注意点
間違えやすい注意点は以下の通り。
まず、現金回収のタイミングと収益認識を混同しないこと。
発生主義では、収益は現金を受け取った時ではなく、「獲得」された(=履行義務が充足された)時点で認識されます。
そして、契約資産(Contract Asset)と売掛金(Accounts Receivable)の違いを理解すること。
売掛金は、支払いを請求する「無条件の」権利がある場合に発生します。
一方、契約資産は、収益は認識したが、他の義務を果たすまで請求する無条件の権利がない場合に発生します。
たとえば、あるソフトウェア会社がライセンス(履行義務1)を先に提供し、導入サービス(履行義務2)が完了するまで代金を請求できない契約を結んだとします。
ライセンスを提供した時点で収益は認識しますが、まだ無条件の請求権はないため「契約資産」を計上します。
その後、導入サービスが完了し、請求書を発行できるようになった時点で、この「契約資産」を「売掛金」に振り替えるわけです。
4. USCPA試験ブループリントにおける収益認識の位置づけ
AICPAが公表するブループリント(出題範囲表)で、収益認識がどのように位置づけられているかを確認しましょう。
(1)FARブループリント
必修科目であるFARでは、収益認識は主にApplication(適用)とRemembering & Understanding(記憶と理解)のスキルレベルで問われます。
これは、基本的な概念の理解と、具体的な計算や仕訳への適用能力が求められることを意味します。
ブループリントに記載されている代表的なタスクは以下の通り。
- Recall concepts of accounting for revenue using the five-step model. (5ステップモデルを用いた収益会計の概念を想起する)
- Determine the amount and timing of revenue to be recognized using the five-step model and prepare journal entries. (5ステップモデルを用いて認識すべき収益の金額とタイミングを決定し、仕訳を作成する)
(2)BARブループリント
選択科目であるBAR(Business Analysis and Reporting)では、収益認識がより高度なAnalysis(分析)のスキルレベルで問われることがあります。
これは、契約書などの資料を解釈し、複雑な状況下で適切な会計処理を判断する能力が求められることを示しています。
代表的なタスクは以下の通り。
- Interpret agreements, contracts and/or other supporting documentation to determine the amount and timing of revenue to be recognized… (契約書やその他補足資料を解釈し、認識すべき収益の金額とタイミングを決定する)
補足:USGAAPとIFRSの違いについて
ASC 606(USGAAP)と IFRS 15(国際財務報告基準)は、FASBとIASBが共同で開発した収斂基準です。
そのため、中核となる原則や5ステップモデルは基本的に同じです。
USCPA試験対策としては、両者に大きな違いはないと理解しておけば十分です。
5. 試験直前!これだけは押さえるべき最終チェックリスト
最後に、試験本番直前に確認すべき収益認識の最重要ポイントをチェックリストにまとめておきますね。
- 収益認識の5ステップモデルを暗唱できるか? (契約の特定 → 履行義務の特定 → 取引価格の決定 → 価格の配分 → 収益の認識)
- 繰延収益(Unearned Revenue)は負債であることを理解しているか? (現金受領時に貸方に計上し、収益認識時に借方に計上して減額する)
- 複数の履行義務がある場合、取引価格を「相対的独立販売価格(SSP)」で配分できるか?
- 長期建設契約の資産/負債の計算式を覚えているか? (発生原価+認識済利益 > 請求額 → 資産、請求額 > 発生原価+認識済利益 → 負債)
- 収益は「支配の移転(Control)」をもって認識されることを理解しているか? (現金回収時点ではない)
以上、「【FAR基礎講座】収益認識(Revenue Recognition)ASC606 解説!USCPA受験生向け」でした。

収益認識は、単なるルール暗記では太刀打ちできない、FARの合否を分ける重要論点だからね。
この記事で解説した5ステップモデルという「思考のフレームワーク」を徹底的にマスターすれば、得意になるよ。
繰り返しトレーニングして、どんな問題にも対応できる応用力を身につけ、自信を持って本番に臨んでね。
もし、BARを選択する場合は、BARで分析レベルの収益認識の学習もがんばってね。
USCPA試験については、どこの著書『USCPA(米国公認会計士)になりたいと思ったら読む本』も参考にしてくださいね。
短期合格のコツも記載しています。
(2026/02/05 09:33:57時点 Amazon調べ-詳細)
まだUSCPAの学習を開始していない場合「USCPAの始めかた」も参考にしてください。