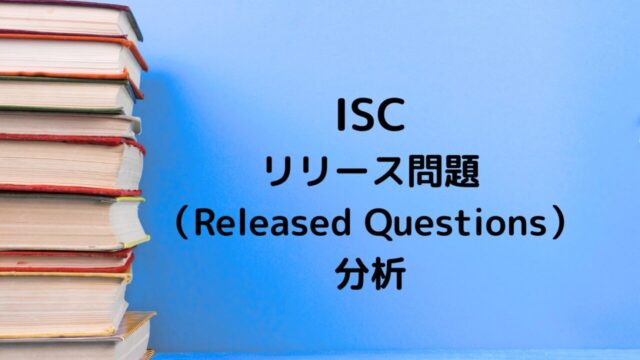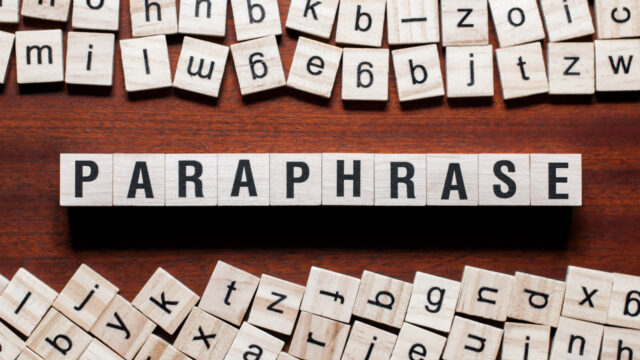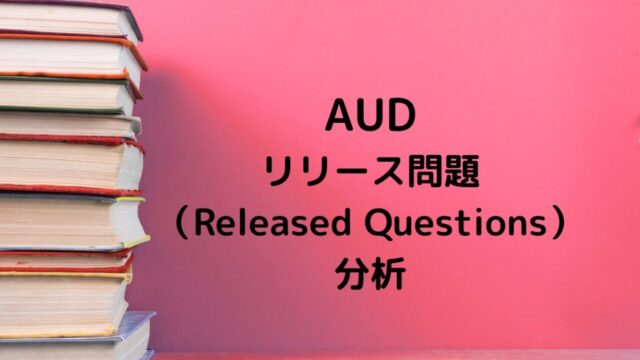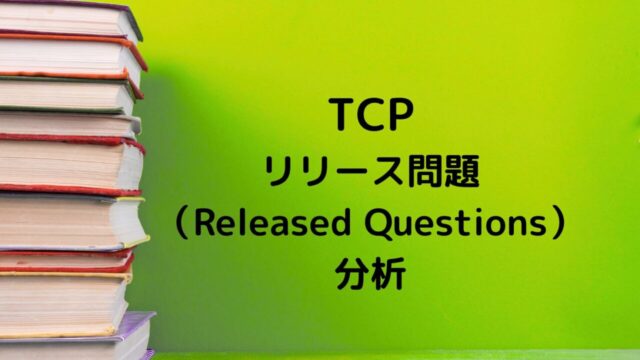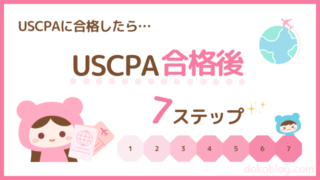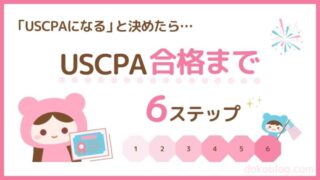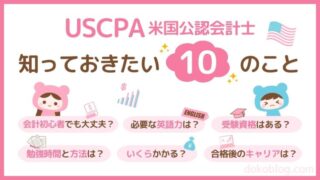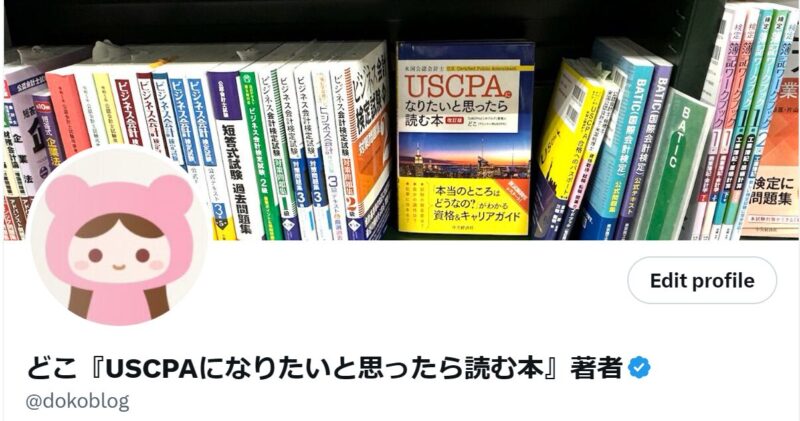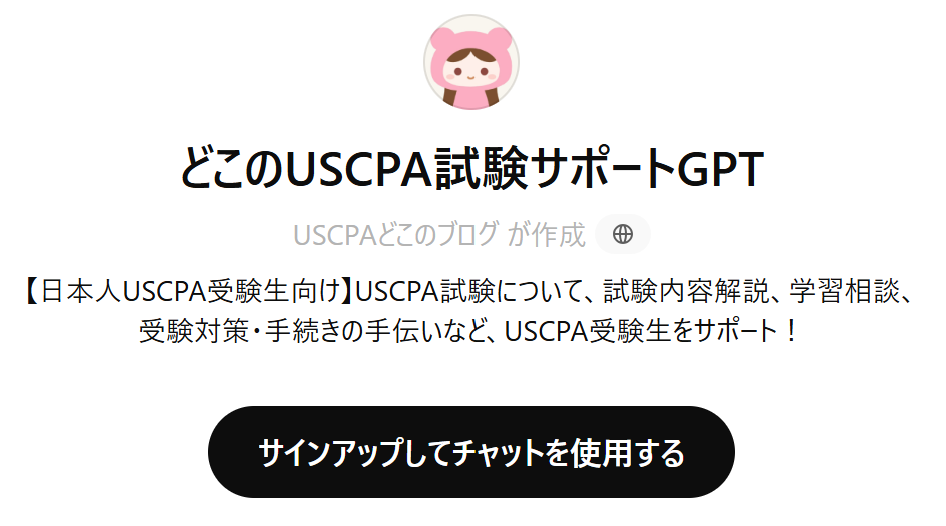【BAR】USCPAリリース問題(AICPA Released Questions)徹底解説
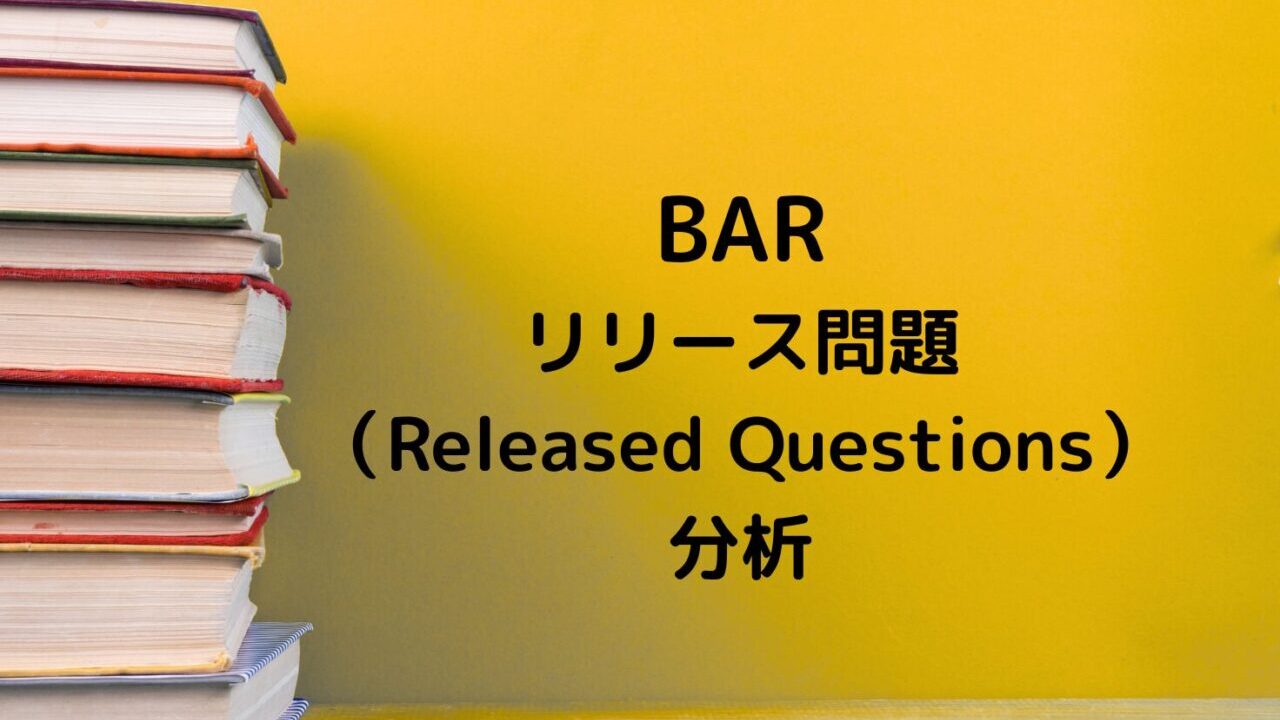

BARのリリース問題(AICPA Released Questions)をやっているけど、何が大事なのかあまりわからないよ。
誰かに解説してもらいたいな。

2019年から2025年までのBARのリリース問題を分析したよ
どのようなトピックが大事なのか、どのように学習すればいいのか解説していくね。
注意:2019年から2023年までは、旧試験のFARとBECからの組み換え問題
まだUSCPA(米国公認会計士)に挑戦してない場合
USCPAは受験資格を満たすのにUSCPA予備校のサポートがマスト。
どこがおすすめするUSCPA予備校はアビタスです。
\無料・すぐ読める・オンライン参加可/
どこの著書『USCPA(米国公認会計士)になりたいと思ったら読む本』も参考にしてくださいね。
USCPA資格の活かしかた・USCPA短期合格のコツを書いています。
(2026/01/15 09:33:51時点 Amazon調べ-詳細)
- 注意:【BAR】USCPAリリース問題(AICPA Released Questions)解説にあたって
- 1.BARで特に重点を置いて学習すべきトピック
- 2.BARリリース問題の出題内容の分析
- 3.BARのリリース問題を基にした理解度チェック
- (1)原価計算 (Cost Accounting)
- (2)財務管理 (Financial Management)
- (3)リスク管理とCOSOフレームワーク (Risk Management & COSO Framework)
- (4)財務会計(GAAP) (Financial Accounting (GAAP))
- ➀ストックオプション会計 (Stock Option Accounting)
- ➁研究開発費 (R&D Costs)
- ③退職給付会計 (Pension Accounting)
- ➃デリバティブ会計 (Derivative Accounting)
- ⑤企業結合会計 (Business Combination Accounting)
- ⑥連結会計 (Consolidation Accounting)
- ⑦外貨換算 (Foreign Currency Translation)
- ⑧セグメント情報 (Segment Reporting)
- ⑨セール&リースバック (Sale-Leaseback)
- ⑩Non-GAAP財務指標 (Non-GAAP Financial Measures)
- ⑪公正価値測定 (Fair Value Measurement)
- (5)政府会計 (Governmental Accounting)
- (6)経済学 (Economics)
- (7) IT/データ分析 (IT/Data Analytics)
- 4.BARのリリース問題に出てくる理解すべき単語
- まとめ:BARのリリース問題で学習ポイントを押さえる
注意:【BAR】USCPAリリース問題(AICPA Released Questions)解説にあたって
BARのUSCPAリリース問題(AICPA Released Questions)の解説をしますが、少しフワッとした部分があるかもしれません。
リリース問題は、権利関係で誰でも入手できるものではありません。
なので、公に問題を1問1問、ネット上に書いていいものではありません。
あくまでも、過去のリリース問題を見て、どのような傾向があるか分析し、お伝えするのが精いっぱいとなります。
少しフワッとしているとしても、USCPA受験生にリリース問題を最大限に活かしていただくため、最大限の努力をしたと、ご理解いただければ幸いです。
当記事では、2019年から2025年までのBARのリリース問題を分析した結果に基づき、BAR受験生が、何をどのように学習したら良いか、解説していきます。
注意:2019年から2023年までは、旧試験のFARとBECからの組み換え問題です。
USCPA試験のリリース問題(AICPAリリース問題)については、こちらの記事が詳しいです。
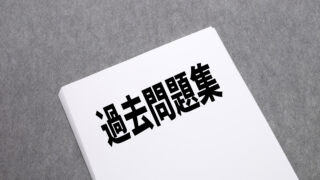
USCPA試験のBAR受験対策徹底解説も参考にしてください。
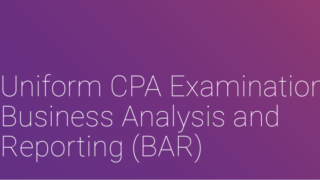
BARのリリース問題解説については、USCPAどこチャンネルの「【BAR】リリース問題(過去問)からの出題傾向解説」も参考にしてください。
1.BARで特に重点を置いて学習すべきトピック
BARのリリース問題(2019年~2025年)を分析した結果、特に何に重点を置いて学習すべきかが明確になっています。
BAR科目は、旧BEC科目の内容に加え、FAR(財務会計報告)科目から再分類された高度な会計トピックが含まれます。
よって、非常に広範囲な知識が求められます
リリース問題を通じて頻繁に出題されている、または、内容が複雑で深い理解が求められるトピックは以下の通りです。
これらを優先的に学習することで、効率的に得点アップを目指せると思いますよ。
注意:あくまでもリリース問題を分析した結果であり、「本番で出題される」または「本番で出題された」というわけではありません。
(1)管理会計・原価計算 (Managerial Accounting & Cost Accounting)
管理会計・原価計算では、以下のようなポイントがあります。
➀差異分析 (Variance Analysis)
直接材料費の数量差異 (Usage Variance) や直接労務費の能率差異 (Efficiency Variance) など、標準原価計算における差異計算が頻繁に出題されます。計算問題が中心です。
➁予算編成 (Budgeting)
変動予算 (Flexible Budget) の作成 や、売上計画から仕入計画・生産計画・資金回収計画を導出する問題 が見られます。
③CVP分析 (Cost-Volume-Profit Analysis)
損益分岐点 (Breakeven Point) や目標利益を達成するための販売量・販売価格の計算、貢献利益 (Contribution Margin) の計算 が繰り返し出題されます。
➃意思決定 (Decision Making)
余剰生産能力がある場合の特別注文 (Special Order) の受注可否判断 や、機会費用 (Opportunity Cost) など、増分原価分析 (Incremental Cost Analysis) を用いた意思決定に関する問題が出ます。
⑤原価配賦 (Cost Allocation)
活動基準原価計算 (Activity-Based Costing; ABC) を用いた製造間接費の配賦計算 も含まれます。
⑥原価計算の概念
全部原価計算と直接原価計算の違い など、基本的な概念理解も問われます。
(2)財務管理 (Financial Management)
財務管理では、以下のようなポイントがあります。
➀財務比率 (Financial Ratios)
流動比率 (Current Ratio) や当座比率 (Quick Ratio)、負債比率 (Debt Ratio)、総資産利益率 (ROA)、売掛金回転日数 (DSO)、株価収益率 (PER)、売上総利益率・純利益率 (Gross/Profit Margin) の計算と解釈が重要です。
取引が比率に与える影響も問われます。
➁運転資本管理 (Working Capital Management)
現金割引の計算 や、運転資本に影響を与える取引の選択 が出題されます。
③資本予算 (Capital Budgeting)
正味現在価値 (NPV) 法、内部収益率 (IRR) 法、割引回収期間法 (Discounted Payback Period) など、投資評価手法に関する計算と概念理解が求められます。
フリーキャッシュフロー (FCF) の計算 や税引後キャッシュフローの計算 も頻出です。
➃資本コスト (Cost of Capital)
加重平均資本コスト (WACC)、普通株式資本コスト (CAPM)、負債資本コスト、優先株式資本コスト の計算が出題されます。
⑤債券 (Bonds)
債券の発行価格と利率の関係 (割引発行)、利払額の計算 に関する問題があります。
⑥デリバティブとヘッジ (Derivatives & Hedging)
先物契約 (Futures Contract) やプットオプション (Put Option) を用いたヘッジ、デリバティブの特性、公正価値ヘッジ やキャッシュフローヘッジ の会計処理に関する問題が出ます。
⑦ストックオプション (Stock Options)
ブラック・ショールズ・モデル (Black-Scholes Model) の前提条件 や、公正価値の算定要素、報酬費用 (Compensation Expense) の計算と認識 が繰り返し問われます。
⑧為替リスク (Foreign Exchange Risk)
為替レートの計算 (クロスレート) や為替変動が事業に与える影響、為替リスクのヘッジ方法 が出題されます。
(3)経済学 (Economics)
経済学では、以下のようなポイントがあります。
➀ミクロ経済学 (Microeconomics)
需要と供給の市場均衡、価格弾力性 (Price Elasticity of Demand) の概念と計算、収益への影響、比較優位 (Comparative Advantage)、規模の経済 (Economies of Scale) が出題されます。
➁マクロ経済学 (Macroeconomics)
連邦債務とインフレの関係、名目値と実質値の変換 (インフレ調整) に関する問題が見られます。
(4)全社的リスクマネジメント (Enterprise Risk Management; ERM)
全社的リスクマネジメントでは、COSO ERMフレームワークがポイントです。
COSO ERMはBARセクションで最も一貫して出題されるテーマの1つ。
フレームワークの構成要素(ガバナンスと文化、戦略と目標設定、パフォーマンス、レビューと改訂、情報・伝達・報告)とその原則、ERMがもたらす便益、リスクの分類 (固有リスク Inherent Risk, 残余リスク Residual Risk)、リスク対応戦略 (受容 Accept, 回避 Avoid, 追求 Pursue, 低減 Reduce, 共有 Share)、不確実性の定義 が幅広く問われます。
(5)情報技術とデータ分析 (Information Technology & Data Analytics)
ITとデータ分析では、以下のようなポイントがあります。
➀データ分析技術 (Data Analytics Techniques)
データマイニングの手法 (クラスタリング Clustering) や記述的分析 (Descriptive Analytics) など、データ分析の基本的な概念と活用方法が出題されます。
➁XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
XBRLの機能や特徴 に関する知識が問われます。
(6)財務会計 (Financial Accounting & Reporting) – BAR再分類項目
FARからの組み換えでは、以下のようなポイントがあります。
➀ソフトウェア会計 (Software Accounting)
販売目的のソフトウェア開発コストの会計処理(研究開発費と資産計上の区分) と償却費の計算(定額法と売上高比例法の比較) が重要です。
➁退職給付会計 (Pension Accounting)
確定給付型制度 (Defined Benefit Plan) と確定拠出型制度 (Defined Contribution Plan) の両方について、負債・資産の認識、財務諸表の作成・表示項目 (Statement of Net Assets Available for Benefits, Statement of Changes in Net Assets Available for Benefits)、会計基準 が問われます。
③企業結合 (Business Combinations)
のれん (Goodwill) の計算 と会計処理 (償却せず減損テスト)、測定期間 (Measurement Period)、取得日 (Acquisition Date)、取得対価の構成要素、非支配持分 (Non-controlling Interest; NCI) の表示、変動持分事業体 (VIE)、非支配株主による支配権への影響 など、重要トピックが多数含まれます。
➃セグメント情報 (Segment Reporting)
報告セグメント (Reportable Segments) を特定するための定量的基準 が問われます。
⑤リース会計 (Lease Accounting)
セール・アンド・リースバック取引の会計処理 が出題されます。
⑥在外子会社会計 (Foreign Currency Translation)
機能通貨 (Functional Currency) の決定、在外子会社の財務諸表換算 (Current Rate Method) が問われます。
(7)政府会計 (Governmental Accounting)
政府会計では、以下のようなポイントがあります。
➀財務報告の構造
政府会計で求められる最低限の財務報告 (Management’s Discussion and Analysis, 基本財務諸表, Required Supplementary Information) や、政府全体財務諸表とファンド財務諸表の関係性 が重要です。
➁ファンド会計
政府会計区分 (Governmental Funds) と企業会計区分 (Proprietary Funds) の違い、それぞれの財務諸表項目 (支出 Expenditures, 正味資産 Net Position)、会計認識基準 (修正発生主義 Modified Accrual Basis) が問われます。
③収益の分類
税収の分類 (Derived Tax Revenue) が出題されます。
➃特定のファンド
資本資産取得ファンド (Capital Projects Funds)、内部サービスファンド (Internal Service Funds)、特別収益ファンド (Special Revenue Funds) などの特徴と会計処理。
⑤予算実績比較表 (Budgetary Comparison Schedule)
記載内容 が問われます。
⑥主要政府 (Primary Government)
定義と要件 も出題されます。
2.BARリリース問題の出題内容の分析
2019年から2025年までのBAR(旧BECからの組み換え含む)のAICPAリリース問題の出題分析をまとめます。
BARセクションのAICPAリリース問題は、旧BECセクションの管理会計、財務管理、経済学、IT(データ分析)に加え、旧FARセクションの財務会計の一部(企業結合、ソフトウェア、年金、政府会計)が組み込まれています。
非常に広範なトピックをカバー。
(1)2019年のBARリリース問題分析
2019年の問題は、BEC科目の典型的な出題範囲と、一部FAR科目からの組み換え問題が含まれています。
➀管理会計
直接労務費能率差異の計算、全部原価計算と直接原価計算の比較、変動予算の作成と固定費・変動費の識別、目標利益達成のためのCVP分析、特別注文の原価計算といった計算問題が多く出題されています。
➁財務管理
現金割引の計算、負債比率や流動比率、正味運転資本の計算と分析、市場リスク評価(Market Value at Risk)、先物契約の経済的実態といった数値計算と概念理解が求められます。
③COSO ERM
ERM導入による便益(リスク対応の強化、資本配分の改善、機会の獲得など)が問われています。
➃国際ビジネス/経済学
多国籍企業における移転価格設定の税務上の考慮、連邦債務増加がインフレ圧力となる理由などが出題されています。
⑤評価/デリバティブ
ブラック・ショールズ・モデルに必要な変数に関する概念問題があります。
⑥財務会計(旧FAR)
以下のように広範囲にわたります。
- ストックオプションの報酬費用認識
- 研究開発費に含めないコスト
- プットオプションの購入理由(ヘッジ目的)
- 確定給付型年金制度の負債認識
- 確定拠出型年金制度の必須財務諸表
- 年金制度の財務諸表における加算要素の計算
- 政府会計における税収の報告区分
- 政府会計一般ファンドの修繕費用計上
- 政府会計の必須財務報告内容
(2)2020年のBARリリース問題分析
2020年のBARリリース問題も、管理会計と財務管理が中心で、経済学、COSO ERM、旧FARからの問題も含まれます。
➀財務比率
流動比率と当座比率を用いた棚卸資産の計算、総資産利益率の改善要因、債務比率によるリスク評価など、計算と解釈が問われています。
➁キャッシュフロー/資本予算
フリーキャッシュフローの計算、IRRとNPVが異なる投資案件の比較評価、プロジェクトの損益分岐点に必要な年間純現金流入の計算などがあります。
③管理会計
直接材料費使用量差異の計算、製造間接費の配賦額計算と差異分析、目標粗利益率からの販売価格設定、目標販売利益率達成のための販売数量計算といった計算問題が引き続き重要です。
➃財務管理/国際ビジネス
加重平均資本コスト(WACC)の計算、為替レート変動による費用の差額計算、為替リスクヘッジの方法(先物契約)、クロスレートの計算、ショートポジションの為替ヘッジが出題されました。
⑤COSO ERM
リスク評価時に考慮すべきリスクの種類、リスク対応戦略の種類、不確実性の定義など、概念的な理解が問われています。
⑥経済学
インフレによる実質コストの変化、価格弾力性と収益への影響、名目価値と実質価値の変換などが出題されています。
⑦財務会計(旧FAR)
以下のように幅広い論点が見られます。
- 販売目的ソフトウェアの償却費計算
- 変動持分事業体(VIE)の主要受益者判断
- デリバティブ金融商品の特徴
- キャッシュフローヘッジの会計処理
- 確定給付型年金制度の資産・負債計上
- 確定拠出型年金制度の投資評価
- 内部サービスファンドの減価償却費報告
- 企業会計区分ファンドの純資産変動計算
- ファンド財務諸表から政府全体財務諸表への調整
(3)2021年のBARリリース問題分析
2021年のBARリリース問題も、計算問題と概念理解の両方がバランス良く出題されています。
➀流動性
流動比率を用いた企業間の流動性比較が問われています。
➁管理会計
売上原価の計算、販売ミックスを考慮した加重平均貢献利益の計算、直接材料費使用量差異の計算、販売計画に基づく仕入予算の計算、確率を用いた売上期待値の計算、変動予算の作成、特別注文の最低販売価格設定(増分原価分析)など、依然として計算が重要です。
③財務管理/デリバティブ
社債の割引発行と市場金利の関係、金利プレミアムの種類(デフォルトリスクプレミアム)、割引回収期間法の計算、複数の投資プロジェクト評価におけるNPV法の優位性、ポートフォリオのリスク分散(完全負の相関)といった概念と計算の両方が出題されました。
➃リスク管理/COSO ERM
リスク評価における優先順位付け(発生確率×影響額)、リスク対応策の費用対効果分析、COSO ERMのリスク対応戦略(共有)など、実務的な応用が問われています。
⑤国際ビジネス/経済学
多国籍企業における移転価格の戦略的利用、市場均衡点、価格弾力性と代替品の入手可能性、比較優位の原則など、経済学の基礎概念が問われます。
⑥財務会計(旧FAR)
以下のように、広範囲にわたります。
- 販売・リース目的ソフトウェアの償却費計算
- ストックオプションの報酬費用認識
- 企業結合におけるのれんの計算
- 機能通貨の決定、在外子会社の換算方法(カレント・レート法)
- 公正価値ヘッジの会計処理
- XBRLの特徴
- セグメント情報の報告基準
- 政府会計の修正発生主義における負債計上
- 資本資産取得ファンドの財務活動の源泉
- 特別収入ファンドの支出計上
(4)2022年のBARリリース問題分析
2022年のBARリリース問題は、財務管理、管理会計、COSO ERM、経済学、旧FAR分野からの問題が均等に出題されています。
➀財務比率/運転資本
流動比率に影響を与える取引の分析、債務返済が運転資本に与える影響など。
➁管理会計
コスト変動に応じた価格再設定の計算、貢献利益を用いた生産継続判断、生産量変化に伴う総原価の変動、過大計上された粗利益率が経営判断に与える影響など、計算と管理会計的思考が問われます。
③財務管理
負債資本コストの計算、社債の利息支払額の計算など。
➃デリバティブ/評価
ブラック・ショールズ・モデルの前提条件に関する概念問題が繰り返し出題されています。
⑤COSO ERM
パフォーマンスガイドラインとCOSO原則の整合性、固有リスクの定義など、概念理解が中心です。
⑥経済学
為替レート変動が事業に与える影響、規模の経済、完全非弾力的供給曲線と需要増加の影響といった経済学の基礎知識が問われます。
⑦財務会計(旧FAR)
以下のようなFAR分野からの組み換え問題が多く見られます。
- のれんの減損テストの実施時期
- 販売目的ソフトウェア開発費の費用認識基準
- 連結財務諸表上の取得日における連結留保利益
- 外貨換算における貸借対照表日の為替レート適用項目
- 公正価値ヘッジの有効性の定義
- 報告セグメントの分類基準
- 確定拠出型年金制度の必須財務諸表
- 政府全体活動計算書の費用表示方法
- 政府会計における派生税収
- 予算実績比較表の必須要素
(5)2023年のBARリリース問題分析
2023年のBARリリース問題も、幅広い分野からの出題が見られ、特に計算問題の複雑さが増しています。
➀データ分析
データマイニング技術(クラスタリング) の概念が問われています。
➁管理会計
能率差異の計算、直接労務費能率差異の計算(有利/不利)、販売量と在庫から生産量予測、損益分岐点売上高の計算など、計算が中心です。
③財務管理/キャッシュフロー
売上債権回転日数と売上変化による売掛金変動率、税引後純キャッシュフローの計算、回帰分析を用いた損益分岐点の計算、加重平均資本コスト(WACC)の計算、NPVを用いたプロジェクト評価など、より実践的な計算問題が出題されています。
➃デリバティブ/評価
株価ボラティリティ増加がコールオプション価値に与える影響(ブラック・ショールズ・モデル)など、概念的な理解が問われます。
⑤COSO ERM
COSO ERMフレームワークの構成要素と原則、効果的なERMの便益(パフォーマンス変動の低減)など。
⑥財務比率
運転資本比率を改善するシナリオ、PER(株価収益率)の解釈など。
⑦経済学
インフレ率を考慮した実質価格上昇率の計算、供給曲線左シフトの影響(価格上昇、数量減少)、価格弾力性を用いた消費量変化の計算、為替リスクヘッジの方法(先物契約の売却)など。
⑧財務会計(旧FAR)
以下のように、FARからの出題も引き続き重点的に見られます。
- 販売目的ソフトウェアの償却額計算
- 企業結合における取得資産の認識(公正価値)
- 無形資産の取得原価と償却
- 非支配株主が支配権に影響を及ぼす事象
- セール・アンド・リースバック取引の会計処理
- 確定拠出年金制度の会計基準(発生主義)
- 政府会計の必須財務諸表
- 企業会計区分ファンドの純投資額計算
- 主要政府の要件
(6)2024年のBARリリース問題分析
2024年のBARリリース問題は、BAR初めてのリリース問題です。
従来のBEC要素に加えて、データ分析やESG関連のリスクマネジメントなど、現代的なトピックが強化されています。
➀データ分析
記述的分析(Descriptive Analytics)の技術(平均値、中央値の計算)が問われています。
➁財務報告
Non-GAAP財務指標の例(中核利益)が概念として出題。
③業績評価
工場の生産効率を示す非財務的指標(製品不良率)の概念。
➃管理会計
活動基準原価計算(ABC)と伝統的原価計算の配賦額の比較、余剰生産能力がある場合の特別注文による利益への影響など、計算問題が特徴的です。
⑤財務管理
資本資産評価モデル(CAPM)による株式の資本コスト計算が出題されています。
⑥資産評価
資産の公正価値の決定(第三者への売却価格)といった概念的な理解が求められます。
⑦COSO ERM / ESG
COSO ERMフレームワークをESGリスクマネジメントに応用する際の推奨行動は、最新のトレンドを反映した重要論点です。
⑧経済学
価格弾力性を用いた物品税導入後の販売数量予測など、計算を伴う経済学の応用問題。
⑨財務会計(旧FAR)
以下のように、依然としてFARからの問題は多岐にわたります。
- のれんの会計処理(減損テストによる損失認識)
- 販売目的ソフトウェア開発コストの研究開発費計上範囲
- ストックオプションの報酬費用認識と計算
- 企業結合の測定期間調整(のれんへの対応)
- 企業結合における対価の構成要素
- 非支配持分の連結財務諸表表示
- 報告セグメントの定量的基準
- 連結を必要としない子会社の状況(法的再編)
- デリバティブの識別(金利スワップ)
- 政府会計のファンド残高分類(”Designated”は不適切)
- 企業会計区分ファンドの純資産計算
- 政府の財務諸表における「管理者による討議と分析(MD&A)」の内容など、
(7)2025年のBARリリース問題分析
2025年のBARリリース問題も、BARセクションの核となる管理会計、財務管理、COSO ERM、そして旧FARからの要素が引き続き出題されています。
➀業績指標
業績指標の適切な利用方法(純営業利益と収益性)といった概念的な理解が求められます。
➁財務分析
ベンチマークを用いた財務パフォーマンス分析(当期純利益率の比較)など、比率計算と解釈が重要です。
③管理会計
活動基準原価計算に基づく配賦原価の計算など、具体的な計算能力が問われます。
➃予算編成/キャッシュフロー
売上予算からの現金回収額の計算といった実務的な計算問題。
⑤財務管理
優先株式の資本コスト計算、資金調達に関する意思決定(機会コスト)、機会コストの概念などが出題されています。
⑥公正価値測定
公正価値ヒエラルキーに基づく公正価値の測定など、重要な概念です。
⑦COSO ERM
COSO ERMフレームワークの構成要素(ビジネス環境理解とリスク選好設定)が引き続き問われます。
⑧財務会計(旧FAR)
以下のように、多岐にわたるトピックが出題されています。
- のれんの償却(非上場企業特例)
- 従業員ストックオプションの公正価値測定要素
- 企業結合の測定期間の会計処理
- 企業結合の取得日
- 支配を必要としない子会社の状況
- デリバティブの判断(金利スワップ)
- キャッシュフローヘッジの会計処理
- 確定拠出型年金制度の純資産変動計算書
- 政府全体財務諸表に含まれないファンド(受託会計区分)
- 企業会計区分ファンドの正味資産表示区分
- 政府ファンド財務諸表から政府全体財務諸表への調整(利息の支出から費用への変換)
3.BARのリリース問題を基にした理解度チェック
BARの2019年から2025年までのAICPAリリース問題を基に、学習すべき内容をまとめました。
BAR(Business Analysis and Reporting)試験は、旧BEC(Business Environment and Concepts)の内容を多く引き継ぎつつ、ビジネス分析と報告に重点を置いています。
過去のリリース問題を分析すると、主に原価計算、財務管理、リスク管理(COSOフレームワーク含む)、財務会計(GAAP)、政府会計、経済学、IT/データ分析の分野が出題されています。
(1)原価計算 (Cost Accounting)
原価計算で理解すべきことは以下の通り。
➀差異分析
- 直接材料費差異: 使用量差異 (materials usage variance) の計算と、不利差異 (unfavorable) か有利差異 (favorable) かの判断を理解することが重要です。
- 直接労務費差異: 能率差異 (direct labor efficiency variance) の計算と、不利差異か有利差異かの判断を習得する必要があります。
- 製造間接費差異: 予定配賦額の計算と、実際製造間接費との比較による過大配賦 (overapplied) または過小配賦 (underapplied) の判断を理解します。
➁全部原価計算と直接原価計算
固定製造間接費が製品原価に含まれるか(全部原価計算)または期間原価として費用化されるか(直接原価計算)の違いを把握し、売上総利益 (gross margin) と貢献利益 (contribution margin) の算出における影響を理解します。
③CVP分析 (Cost-Volume-Profit Analysis)
- 損益分岐点 (break-even point) や目標利益を達成するために必要な販売数量の計算方法。
- 総原価が変動費と固定費で構成されることを理解し、生産量変化に伴う総原価の計算ができるようにします。
➃予算編成
- 変動予算 (flexible budget): 生産水準に合わせて変動費を比例的に調整し、固定費を一定とみなして予算を作成する方法を理解します。
- 販売計画に基づいた購買計画の計算方法 および生産数量と期末・期首在庫の関係を把握します。
⑤増分原価分析による意思決定
特別注文 (special order) の受諾可否: 余剰生産能力がある場合、最低受注価格は変動費をカバーできる範囲で判断されるという原則を理解します。固定費は既存の生産で回収されているため、特別注文の判断には影響しません。
⑥活動基準原価計算 (Activity-Based Costing, ABC)
コストドライバー (cost driver) に基づいて製造間接費を配賦する方法と、従来の配賦方法との違いが与える影響を計算し理解します。
暗記すべきことは、以下の通りです。
- 各種差異分析の基本的な計算式。
- 全部原価計算と直接原価計算における原価の分類の概念。
(2)財務管理 (Financial Management)
財務管理で理解すべきことは、以下の通り。
➀財務比率分析
- 流動性比率: 流動比率 (current ratio) と当座比率 (quick ratio) の計算方法を理解し、取引がこれらの比率にどう影響するかを分析できるようにします。
- 安全性比率: 負債比率 (debt ratio) を計算し、債権者視点でのリスクを評価する方法を理解します。
- 収益性比率: 総資産利益率 (ROA) の改善要因、売上総利益率 (gross margin ratio)、純利益率 (profit margin) などの計算と企業パフォーマンスの分析。
➁運転資本管理 (Working Capital Management)
- 買掛金の早期支払いによる現金割引 (cash discount) の計算。
- 運転資本 (working capital) および流動比率の増減に影響を与える取引を特定する能力。
- 売掛金回転日数 (Days Sales Outstanding, DSO) の変化が売掛金残高に与える影響の計算。
③資本コスト (Cost of Capital)
- 加重平均資本コスト (WACC): 株主資本コストと負債コストを加重平均して計算する方法。
- 負債コスト: 実効税率を考慮した負債のコストの計算。
- 優先株式の資本コスト: 配当額と発行価額に基づく計算。
- 資本資産評価モデル (CAPM): 株式の期待収益率を計算する公式を理解し適用します (Ki = Kf + β(Km – Kf))。
➃投資意思決定 (Investment Decision Making)
- 正味現在価値法 (NPV) と内部収益率法 (IRR): 相互に排他的なプロジェクトの場合、NPVが最大のプロジェクトを選択することが最も有利であるという原則。プロジェクト期間や投資額が異なる場合にIRRとNPVが異なる順位付けをする可能性があることを理解します。
- 割引回収期間法 (Discounted Payback Period): 投資回収にかかる期間の計算。
- フリーキャッシュフロー (FCF): 営業活動によるキャッシュフローから投資活動によるキャッシュフローを差し引いた概念を理解し、計算できるようにします。
- 税引後ネットキャッシュフローの計算。
⑤リスクとリターン
- 投資ポートフォリオにおけるリスク分散の概念を理解し、特に完全に負の相関関係にある株式がポートフォリオのリスクを最も低減すること。
- 市場における価格変動へのエクスポージャーを評価する「Market Value at Risk Analysis」のような手法の目的。
- デフォルトリスクプレミアムなど、リスクの種類ごとのプレミアムを識別します。
⑥為替リスク管理 (Foreign Exchange Risk Management)
- 為替レートの変動(実質減価・増価)が輸入品や国産品の価格に与える影響を理解します。
- 異なる通貨間のクロスレートの計算方法。
- 将来の為替変動リスクをヘッジするための手段、特に為替予約取引 (forward contract) や先物契約 (futures contract) の利用方法を理解します。
⑦機会コスト (Opportunity Cost)
- ある選択肢を選んだときに放棄される最大の利益という概念を理解し、具体的な意思決定シナリオで機会コストを識別・計算できるようにします。
暗記すべきことは、以下の通りです。
- 主要な財務比率(流動比率、当座比率、負債比率、ROA)の計算式と意味。
- NPVとIRRが異なる順位付けをする具体的な状況。
- 主要な為替リスクヘッジの手段。
- 資本コスト(WACC、CAPM)の計算式。
(3)リスク管理とCOSOフレームワーク (Risk Management & COSO Framework)
リスク管理とCOSOフレームワークで理解すべきことは、以下の通り。
➀COSO-ERMの便益
ERMを組織の戦略策定やパフォーマンス管理と統合することで得られる便益(機会の範囲拡大、ネガティブサプライズの削減、経営資源配分の改善、パフォーマンス変動の低減など)を理解します。
➁リスク評価 (Risk Assessment)
- リスクは、その発生する可能性 (likelihood) と発生した場合の影響の深刻さ (severity) の両方を掛け合わせて評価されることを理解し、優先順位付けの計算ができるようにします。
- 固有リスク (inherent risk): 経営陣がリスクの発生可能性や影響を変えるための行動を取らない状態でのリスクを指すという定義を理解します。
- ERMフレームワークにおいて、固有リスク、目標残余リスク (target residual risk)、実際残余リスク (actual residual risk) がリスク評価の際に考慮される要素であることを把握します。
③リスク対応 (Risk Response)
COSO-ERMが示す5つのリスク対応戦略(受容 (accept)、回避 (avoid)、追求 (pursue)、低減 (reduce)、共有 (share))の概念と、それぞれの例を理解します。
➃ERMの構成要素と原則
- COSO-ERMの5つの相互に関連する構成要素(ガバナンスと文化、戦略と目標設定、パフォーマンス、レビューと改訂、情報・伝達・報告)を理解します。
- 特に、「全社的リスクマネジメント改善の追求 (Pursues improvement in enterprise risk management)」の原則が「レビューと改訂 (Review & Revision)」の構成要素に含まれることを把握します。
- 「ビジネス環境の理解を通じて、組織は内的・外的要因に関する洞察を得て、それに応じてリスク選好度を設定できる」という記述が「戦略と目標設定 (Strategy & Objective-setting)」の構成要素に該当することを理解します。
⑤不確実性 (Uncertainty)
ERMにおける不確実性が「潜在的な事象がどのように、または実際に顕在化するか分からない状態」を指すことを理解します。
⑥ESG関連リスクのERMへの応用
ESGリスクマネジメントにおいて、価値創造プロセスとビジネスモデルを検証し、組織のあらゆる形態の資本(ヒト・モノ・カネ)に与える短期・中期・長期の影響と依存関係を理解することが推奨される行動であることを認識します。
暗記すべきことは、以下の通りです。
- COSO-ERMの5つの構成要素の名称とその主要な原則。
- リスクの定義(固有リスク、残余リスク)。
- リスク対応の5つの戦略の名称とそれぞれの意味。
(4)財務会計(GAAP) (Financial Accounting (GAAP))
財務会計で理解すべきことは、以下の通りです
➀ストックオプション会計 (Stock Option Accounting)
- 報酬費用の認識: ストックオプションの報酬費用は、付与日 (grant date) における公正価値 (fair value) に基づいて測定され、必要なサービス期間 (requisite service period) にわたって均等に (ratably) 費用として認識されることを理解し、計算できるようにします。
- Black-Scholesモデル: オプション価格算出に必要な変数(行使価格、残存期間、共通株価格、ボラティリティ、金利) と、モデルの仮定(取引コストなし、リスクフリーレートはオプション期間を通じて一定)を理解します。株価のボラティリティの増加がコールオプションの価値を増加させる理由を理解します。
➁研究開発費 (R&D Costs)
- 一般管理費は研究開発費には含まれないことを理解します。
- 販売目的ソフトウェアの開発コスト: 技術的可能性 (technological feasibility) が確立されるまでのコストは研究開発費として費用認識され、確立後のコストは無形資産として資産計上され、その後に償却されるという会計処理の原則を理解します。償却額は、予想総収益に対する当期売上の割合に基づく金額と定額法による金額のいずれか大きい方で計算されます。
③退職給付会計 (Pension Accounting)
- 確定給付型制度 (Defined Benefit Plan): 貸借対照表における負債(または資産)の認識は、予測給付債務 (projected benefit obligation, PBO) と制度資産 (plan assets) の公正価値の差額に基づくことを理解します。
- 確定拠出型制度 (Defined Contribution Plan): 必要な財務諸表として「給付のために利用可能な純資産計算書 (Statement of net assets available for benefits)」と「給付のために利用可能な純資産の変動計算書 (Statement of changes in net assets available for benefits)」があること。投資は公正価値で計上されること。確定拠出型年金制度の財務諸表は発生主義 (accrual basis) に基づいて作成されること。
➃デリバティブ会計 (Derivative Accounting)
- デリバティブが満たすべき3つの主要な特徴(1つ以上の基礎変数に基づく、少額の初期投資、差金決済が可能)を理解します。
- 公正価値ヘッジ (Fair Value Hedge): ヘッジ対象とデリバティブの公正価値の変動が損益計算書 (earnings) に認識され、相殺される会計処理を理解します。ヘッジ有効性 (hedge effectiveness) の定義を理解します。
- キャッシュフローヘッジ (Cash Flow Hedge): オプションの価値の変動のうち有効な部分がその他の包括利益 (Other Comprehensive Income, OCI) で計上される会計処理を理解します。
⑤企業結合会計 (Business Combination Accounting)
- のれん (Goodwill): 取得企業が支払った対価の公正価値が、被取得企業の識別可能純資産 (identifiable net assets) の公正価値を超過する金額として認識されることを理解します。
- 減損テスト: のれんは償却されず、少なくとも年1回、毎年同じ時期に減損テストを実施する必要があることを理解します。非上場企業の場合、10年を上限として償却する代替方法を選択できることを把握します。
- 取得関連コスト: コンサルティング費用やデューデリジェンス費用などの取得関連コストは、発生時に費用として認識され、取得原価には含めないことを理解します。
- 測定期間 (Measurement Period): 取得日から1年を超えない範囲で、取得日時点の事実と状況に関する新たな情報に基づいて、暫定的に認識された金額(のれんなど)を調整できる期間を理解します。
- 対価 (Consideration Transferred): 支払いに用いる現金、発行する自社株(公正価値)、条件付対価(公正価値)が含まれることを理解します。
- 取得日 (Acquisition Date): 通常は契約上の完了日 (closing date) であることを理解します。
⑥連結会計 (Consolidation Accounting)
- 非支配持分 (Noncontrolling Interest, NCI): 連結貸借対照表上、資本 (equity) の一項目として別途表示されることを理解します。
- 支配 (Control): 過半数の議決権を有していても、非支配株主が通常の事業過程における意思決定を阻止する権利を持つ場合など、支配が及ばないと見なされるケースがあることを理解します。子会社が法的再編中の場合も支配が存在するとみなされ連結対象となること。
- 連結留保利益: 取得日時点では、親会社の留保利益のみが連結留保利益となることを理解します。
⑦外貨換算 (Foreign Currency Translation)
- 機能通貨 (functional currency): 子会社が活動する経済的環境で主たる収入・支出のために使用する通貨であることを理解します。
- カレント・レート法 (current rate method): 機能通貨が現地通貨の場合、資産・負債は決算日レート (current rate) で、収益・費用は加重平均為替レート (weighted average rate) で換算されることを理解し、計算できるようにします。
⑧セグメント情報 (Segment Reporting)
報告対象セグメント (reportable segment) の定量的基準(総資産、総収益、営業損益の絶対値のいずれかが全体の10%以上)を理解します。
⑨セール&リースバック (Sale-Leaseback)
オペレーティングリースに該当する場合の会計処理、特に現金収入、売却損益、使用権資産、リース負債の仕訳を理解します。
⑩Non-GAAP財務指標 (Non-GAAP Financial Measures)
GAAPで定義されていない財務指標(例:中核利益 (core earnings))の概念と目的を理解します。
⑪公正価値測定 (Fair Value Measurement)
- 公正価値の定義。
- 公正価値ヒエラルキーにおいて、観察可能なインプット(レベル1)が最も優先され、次に観察可能なインプットから導出されたインプット(レベル2)が続くことを理解します。
暗記すべきことは、以下の通りです。
- ストックオプション報酬費用の計上期間と評価基準
- ソフトウェア開発費用の資産計上・費用計上の境界となる技術的可能性の確立
- デリバティブの3つの特徴
- のれんの償却ルール(原則償却なし、年1回減損テスト)
- 外貨換算のカレント・レート法における資産・負債と収益・費用の換算レート
- 報告対象セグメントの10%基準
- Non-GAAP財務指標の例(中核利益)
(5)政府会計 (Governmental Accounting)
政府会計で理解すべきことは、以下の通りです。
➀基本財務諸表 (Basic Financial Statements)
- 「管理者による討議と分析 (Management’s Discussion and Analysis, MD&A)」、基本財務諸表と注記、必須補足情報 (Required Supplementary Information, RSI) が政府の財務報告の最低限開示情報であることを理解します。
- MD&Aに記載されるべき主な情報(財務諸表の簡単な説明、要約財務情報、財政状態と経営成績の分析など)を把握します。
➁政府全体財務諸表 (Government-wide Financial Statements)
- 活動計算書 (Statement of Activities): 税収は一般収益 (general revenues) として報告されること。費用は機能 (function) 別に報告されること。
- 受託会計区分 (fiduciary funds) の金額は政府全体財務諸表には含まれないこと。
③ファンド財務諸表 (Fund Financial Statements)
政府会計区分 (Governmental Funds)は以下の通り。
- 修正発生主義 (modified accrual basis) が適用されること。
- 負債は年度末後短期間で決済される必要がある場合にのみ計上されること。
- 固定資産の取得費用は支出 (expenditures) として報告され、減価償却費は計上されないこと。
- 債券発行収入や他ファンドからの移転がその他の資金源 (other financing sources) として計上されること。
- ファンド残高 (fund balances) は、支出不能、使途制限付き(外部/内部)、使途割り当て済み、使途制限なしに区分されること。
企業会計区分 (Proprietary Funds)は、以下の通り。
- 発生主義 (accrual basis) と経済的資源測定焦点 (economic resources measurement focus) に基づいて会計処理されること。
- 減価償却費は営業費用 (operating expense) として報告されること。
- 純資産 (net position) は、「関連債務差引後の資本資産への純投資額」「使途制限のある正味資産」「使途制限のない正味資産」の3つの構成要素で表示されること。純資産の計算もできるようにします。
➃政府全体財務諸表への調整 (Reconciliation to Government-wide Financial Statements)
ファンド財務諸表で計上された支出(例:固定資産取得額、利息支払額)を、政府全体財務諸表で認識される資産と費用(減価償却費、利息費用)に調整する方法を理解します。
⑤主要政府 (Primary Government)
独立して選出された管理機関を持つことなど、主要政府の要件を理解します。
⑥予算実績比較表 (Budgetary Comparison Schedule)
必須要件として、当初予算額、最終予算額、実績額が含まれること。差異の表示は必須ではなく、奨励項目であること。
⑦派生税収 (Derived Tax Revenue)
売上税や所得税など、交換性取引から派生して得られる税収の概念を理解します。
暗記すべきことは、以下の通りです。
- 政府会計の基本となる会計基準(修正発生主義、発生主義)の適用範囲。
- 各ファンド(政府会計区分、企業会計区分)の主要な表示内容。
- 政府全体財務諸表とファンド財務諸表の間での主要な調整項目。
- 政府会計におけるファンド残高および純資産の区分名称。
(6)経済学 (Economics)
経済学で理解すべきことは、以下の通り。
➀インフレ (Inflation)
- 連邦債務の増加がマネーサプライの増加を通じてインフレ圧力を形成するメカニズムを理解します。
- 名目値と実質値の概念を理解し、インフレ率を考慮して実質的な価格変化やキャッシュフローを計算できるようにします。
➁需要と供給 (Supply and Demand)
- 市場均衡 (market equilibrium) が需要と供給が交わる点で達成されること。
- 供給曲線のシフト(特に代替品がない状況での左シフト)が、均衡価格の上昇と均衡数量の減少をもたらすこと。
- 供給が価格に対して完全に非弾力的な場合、需要の増加が価格の上昇と数量の一貫性を生むこと。
③需要の価格弾力性 (Price Elasticity of Demand)
- 価格弾力性係数 (E) の定義(価格の変化率に対する需要量の変化率の比)と、E > 1 (弾力的) の場合、価格を上げると売上収益が減少すること、E < 1 (非弾力的) の場合、価格を下げても売上収益が減少すること。
- 代替財の利用可能性が高いほど、価格弾力性が高くなるという関係を理解します。
➃比較優位 (Comparative Advantage)
国際貿易や専門化の文脈で、各経済主体が最も効率的に生産できるものを生産すべきという原則を理解し、生産計画の最適化に応用します。
⑤規模の経済 (Economies of Scale)
投入量 (input) の増加率よりも生産量 (output) の増加率が大きい場合に発生する、平均費用の低下現象を理解します。
⑥移転価格 (Transfer Pricing)
多国籍企業が法人税率の異なる国間で利益を最適化するために、移転価格を設定する理由を理解します(税率の低い国に利益を移すために、その国への販売価格を高く設定するなど)。
⑦株価収益率 (Price-Earnings Ratio, PER)
PERが高い企業は、投資家が将来の利益成長に高い期待を抱いていることを示唆するという概念を理解します。
暗記すべきことは、以下の通りです。
- 需要の価格弾力性の定義と、それが総収益に与える影響のパターン
- 基本的な需要曲線と供給曲線のシフトが均衡価格と均衡数量に与える影響
(7) IT/データ分析 (IT/Data Analytics)
IT/データ分析で理解すべきことは、以下の通りです。
➀XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
財務報告を電子化し、効率化や比較・分析を可能にするための言語であり、入力される数値にタグを付けて標準化するという特徴を理解します。
➁データマイニング技術 (Data Mining Techniques)
クラスター分析 (clustering): データに隠されたパターンを見つけてグループに分類する手法であり、特定の地域に集中する顧客グループの購買傾向の特定などに使用されることを理解します。
アソシエーション分析や予測分析といった他のデータマイニング手法の目的も把握します。
③記述的分析 (Descriptive Analytics)
過去のデータを要約し、平均値や中央値などの統計量を用いて傾向を分析する手法であり、過去の販売データの分析に役立つことを理解します。
暗記すべきことは、以下の通りです。
- XBRLの主要な特徴(タグ付けによるデータ定義)
- 主要なデータマイニング手法の目的(特にクラスター分析)
これらのポイントを体系的に学習し、計算問題の練習を重ねることで、BAR試験のAICPAリリース問題への理解を深めることができます。
4.BARのリリース問題に出てくる理解すべき単語
BARのリリース問題に出てくる単語で、理解しておくべきものをまとめておきます。
- 活動基準原価計算 (Activity-Based Costing, ABC): 活動(コストドライバー)に基づいて間接費を製品やサービスに配賦する原価計算システム。
- 追加払込資本 (Additional Paid-in Capital, APIC): 株式の額面価格を超える金額で発行された株式から生じる資本。
- 累積給付債務 (Accumulated Benefit Obligation, ABO): 現在の給与水準に基づいて計算された、従業員に対する確定給付年金制度の債務。
- 実際残余リスク (Actual Residual Risk): 経営者がリスクの重大性を変えるための行動を取った後に残っているリスク。
- 取得日 (Acquisition Date): 事業結合において、取得企業が被取得企業を実質的に支配する日。
- 取得関連コスト (Acquisition-Related Costs): 企業結合に関連して発生する費用で、取得原価には含まれず、発生時に費用処理される。
- 獲得コスト (Acquisition Costs): 資産を取得するために発生した費用。
- 割当済ファンド残高 (Assigned Fund Balance): 政府内部の意思決定機関によって特定の目的のために意図された、使途制限のないファンド残高。
- アソシエーション分析 (Associations): データ間の関連性やパターンを特定するデータマイニング手法。
- 利用可能販売有価証券 (Available-for-Sale Securities): 売却を目的として保有されるが、売買目的有価証券には分類されない債務証券または株式証券。
- ブラック・ショールズ・モデル (Black-Scholes Model): オプションの理論価格を算定するための数理モデル。
- 損益分岐点 (Break-Even Point): 総収益が総費用に等しくなり、利益も損失も発生しない販売量または売上高。
- 予算実績比較表 (Budgetary Comparison Schedules): 政府機関が予算と実績を比較して報告する補足情報。
- 資本資産取得ファンド (Capital Projects Funds): 大規模な一般資本資産の取得または建設を管理するために使用される政府会計ファンド。
- 資本資産評価モデル (Capital Asset Pricing Model, CAPM): 資産の期待収益率とリスクの関係を示すモデル。
- キャッシュ・コンバージョン・サイクル (Cash Conversion Cycle): 企業が投下した現金が売上を通じて現金として回収されるまでの期間。
- キャッシュフロー・ヘッジ (Cash Flow Hedge): 資産、負債、または確定した約因のキャッシュフローの変動リスクを相殺するために使用されるヘッジ。
- クラスター分析 (Clustering): データに隠されたパターンを見つけてグループに分類するデータ解析手法。
- コミット済ファンド残高 (Committed Fund Balance): 政府内部の最高意思決定機関によって特定の目的のために正式に指定されたファンド残高。
- 比較優位 (Comparative Advantage): ある財を他国よりも低い機会費用で生産できる能力。
- 報酬費用 (Compensation Expense): ストック・オプションなどの従業員報酬に関連して認識される費用。
- 包括年次財務報告書 (Comprehensive Annual Financial Report, CAFR): 地方政府の財務報告の最上位レベル。
- 連結財務諸表 (Consolidated Financial Statements): 親会社とその子会社の財務状況および業績を単一の経済エンティティとして表示する財務諸表。
- 条件付対価 (Contingent Consideration): 企業結合において、将来の特定のイベントの発生や条件の達成に基づいて支払われる追加の対価。
- 貢献利益 (Contribution Margin): 売上高から変動費を差し引いた金額で、固定費を賄い、利益を生み出すために利用できる金額。
- 貢献利益率 (Contribution Margin Ratio): 売上高に対する貢献利益の割合。
- 支配 (Control): 親会社が子会社の財務および経営方針を指示する能力。
- 中核利益 (Core Earnings): 企業の主要な事業活動から発生する利益で、非反復的な項目を除外して計算される非GAAP指標。
- COSOエンタープライズリスクマネジメント (COSO Enterprise Risk Management, COSO-ERM): 企業がリスクを管理し、戦略的目標を達成するためのフレームワーク。
- クーポーン・レート (Coupon Rate): 債券の額面価格に対する年間利息の割合。
- 当座比率 (Current Ratio): 流動資産を流動負債で割った比率で、企業の短期的な流動性を示す。
- データマイニング (Data Mining): 大量のデータからパターンや傾向を発見するプロセス。
- 負債比率 (Debt Ratio): 総資産に対する負債の割合。
- 繰延流入 (Deferred Inflows of Resources): 政府会計において、将来の期間に収益として認識される資源の流入。
- 繰延流出 (Deferred Outflows of Resources): 政府会計において、将来の期間に費用として認識される資源の流出。
- 確定給付年金制度 (Defined Benefit Pension Plan): 従業員が退職後に受け取る年金給付額が事前に定められている年金制度。
- 確定拠出年金制度 (Defined Contribution Pension Plan): 雇用主が従業員の口座に拠出する金額が事前に定められている年金制度。
- 需要の価格弾力性 (Demand Elasticity of Price): 価格の変化に対する需要量の反応度合いを示す指標。
- 派生税収 (Derived Tax Revenue): 売上税や所得税など、交換性取引から派生して得られる税収。
- 記述的分析 (Descriptive Analytics): 過去のデータを要約し、何が起こったかを記述する分析手法。
- ディスカウント回収期間法 (Discounted Payback Method): 将来のキャッシュフローを割引いて、初期投資を回収するのにかかる期間を計算する投資評価手法。
- 規模の不経済 (Diseconomies of Scale): 生産量が増加するにつれて、平均費用が増加する現象。
- 需要曲線 (Demand Curve): 所与の価格で消費者が購入しようとする財の量を示すグラフ。
- 減損テスト (Impairment Test): 資産の回収可能価額が帳簿価額を下回っているかどうかを判断するプロセス。
- 賦課による非交換性収益 (Imposed Nonexchange Revenues): 財産税など、交換を伴わない政府によって課される収益。
- インフレ・プレミアム (Inflation Premium): インフレによる購買力の低下を補償するために必要な金利の追加分。
- 固有リスク (Inherent Risk): 内部統制が存在しないと仮定した場合に存在するリスク。
- 内部収益率 (Internal Rate of Return, IRR): プロジェクトの正味現在価値(NPV)がゼロになる割引率。
- 金利スワップ (Interest Rate Swap): 異なる種類の金利(固定と変動など)の交換を取り決める金融契約。
- 内部サービスファンド (Internal Service Funds): 政府内で他の部門に財やサービスを提供する活動を会計処理するために使用される企業会計ファンド。
- 本源的価値 (Intrinsic Value): オプションの行使によってすぐに実現できる利益。
- のれん (Goodwill): 企業結合において、取得対価が被取得企業の識別可能純資産の公正価値を超過する部分。
- 売上総利益 (Gross Margin): 売上高から売上原価を差し引いた金額。
- 売上総利益率 (Gross Margin Ratio): 売上高に対する売上総利益の割合。
- ヘッジ会計 (Hedge Accounting): ヘッジ対象の公正価値またはキャッシュフローの変動をヘッジ手段の変動と相殺して認識する会計処理。
- 歴史的レート (Historical Rate): 過去の取引日に存在した為替レート。
- 棚卸資産回転日数 (Days in Inventory): 棚卸資産が販売されるまでに平均してかかる日数。
- 棚卸資産回転率 (Inventory Turnover): 売上原価を平均棚卸資産で割った比率で、棚卸資産がどれだけ効率的に販売されているかを示す。
- 公正価値ヒエラルキー (Fair Value Hierarchy): 公正価値測定に使用されるインプットの観察可能性に基づく3つのレベルの分類。
- 公正価値ヘッジ (Fair Value Hedge): 認識された資産または負債の公正価値の変動リスクを相殺するために使用されるヘッジ。
- ファンド財務諸表 (Fund Financial Statements): 政府会計において、政府活動の種類や特定の目的に応じて作成される財務諸表。
- 機能通貨 (Functional Currency): 企業が主要な経済活動を行う環境で使用される通貨。
- 政府全体財務諸表 (Government-Wide Financial Statements): 政府の全ての活動を統合して表示する包括的な財務諸表。
- 加重平均資本コスト (Weighted-Average Cost of Capital, WACC): 企業の資本構造におけるすべての資本源(債務、普通株式、優先株式)の加重平均コスト。
- XPBL (eXtensible Business Reporting Language): 財務報告データにタグ付けし、コンピュータによる比較・分析を可能にするXMLベースの言語。
- 流動性 (Liquidity): 企業が短期債務を履行する能力、または資産を現金に迅速に変換できる能力。
- 流動比率 (Current Ratio): 流動資産を流動負債で割った比率。
- 正味運転資本 (Working Capital): 流動資産から流動負債を差し引いた金額。
- 市場均衡 (Market Equilibrium): 需要量と供給量が等しくなる状態。
- マーケット・バリュー・アット・リスク分析 (Market Value at Risk Analysis): 市場価格の変動によるポートフォリオの潜在的な損失を測定するリスク管理手法。
- 測定期間 (Measurement Period): 企業結合において、取得日における暫定的な金額を修正するために認められる期間(最長1年)。
- 修正発生主義 (Modified Accrual Basis): 政府会計ファンドで一般的に使用される会計処理方法。
- 貨幣性資産/負債 (Monetary Asset/Liability): 金額が固定された現金、または現金で受け取る/支払うことが固定された資産や負債。
- 正味現在価値 (Net Present Value, NPV): プロジェクトの将来キャッシュフローの現在価値から初期投資を差し引いた金額。
- 正味運転資本 (Net Working Capital): 流動資産から流動負債を差し引いた金額。
- 非支配持分 (Non-Controlling Interest, NCI): 連結子会社の純資産のうち、親会社以外の株主に帰属する部分。
- 非GAAP財務指標 (Non-GAAP Financial Measures): 一般に公正妥当と認められた会計原則(GAAP)で定義されていない財務指標。
- 非交換性取引収益 (Nonreciprocal Interfund Activities): 政府会計において、対価を伴わないファンド間の資金移転。
- 想定元本 (Notional Amount): デリバティブ契約の計算に使用される参照額。
- 機会費用 (Opportunity Cost): ある選択肢を選んだために放棄することになる、次善の選択肢から得られたであろう最大の利益。
- オプション価格評価モデル (Option Pricing Model): オプションの公正価値を評価するための数理モデル。
- その他の包括利益 (Other Comprehensive Income, OCI): 損益計算書に含まれないが、純利益とともに包括利益を構成する項目。
- その他のファイナンス源泉 (Other Financing Sources): 政府会計において、債務の発行や他のファンドからの移転など、通常の収益ではない資金源。
- 素価 (Prime Costs): 直接材料費と直接労務費の合計。
- プライマリー・ベネフィシャリー (Primary Beneficiary): 変動持分事業体(VIE)の経済的活動に最も重要な影響を及ぼす活動内容を指揮する権限を持つ企業。
- 予測給付債務 (Projected Benefit Obligation, PBO): 将来の給与水準を考慮して計算された、従業員に対する確定給付年金制度の債務。
- 事業型活動 (Proprietary Activities): 市民に財やサービスを提供する政府活動。
- 企業会計区分 (Proprietary Funds): 財やサービスの提供を通じて収益を生み出す政府活動を会計処理するために使用されるファンド。
- プットオプション (Put Option): 特定の資産を事前に定められた価格で売却する権利。
- 準資本 (Quasi-Equity): 負債と資本の間に位置付けられる、資本に類似した性質を持つ項目。
- 再投資率 (Reinvestment Rate): プロジェクトから生じるキャッシュフローが再投資されると予想されるレート。
- 関連債務差引後の資本資産への純投資額 (Invested in Capital Assets, Net of Related Debt): 資本資産の帳簿価額から関連債務を差し引いた、企業会計ファンドの純資産の一部。
- 報告セグメント (Reportable Segments): 収益、利益/損失、資産のいずれかの定量的基準を満たし、財務諸表で個別に開示が求められる事業セグメント。
- 必要勤務期間 (Requisite Service Period): ストック・オプションなどの従業員報酬が確定するために従業員が勤務しなければならない期間。
- 研究開発費 (Research and Development Costs): 新製品やプロセスの研究・開発に関連して発生する費用。
- 残余利益 (Residual Income): 営業利益から投下資本の資本コストを差し引いた金額。
- 受託会計区分 (Fiduciary Funds): 政府が個人や組織のために資産を保有・管理する活動を会計処理するために使用されるファンド。
- リスク選好 (Risk Appetite): 企業が特定の目標を達成するために受け入れる用意のあるリスクの量。
- リスク・プレミアム (Risk Premium): 無リスク金利に加えて、特定のリスクを負うことに対する報酬として要求される追加の収益。
- セール・アンド・リースバック (Sales-Leaseback): 資産を売却し、同時にその資産をリースバックする取引。
- 販売目的のソフトウェア (Software to be Sold): 販売またはリースを目的として開発されたソフトウェア。
- 特別賦課金 (Special Assessments): 特定の改善から利益を得るために、特定の受益者に課される税金。
- 特別項目 (Special Items): 通常の営業活動から独立しているが、異常な性質またはまれな発生頻度を持つ事象。
- スポット価格 (Spot Price): 即時受渡しで行われる取引の現在の市場価格。
- 標準原価計算 (Standard Costing): 製品やサービスの標準原価を設定し、実際原価との差異を分析する原価計算システム。
- 標準時間 (Standard Hours): 特定の生産レベルを達成するために予想される労働時間。
- 標準賃率 (Standard Rate): 労働時間に対して支払われる標準的な賃金率。
- 静的予算 (Static Budget): 特定の活動レベルに基づいて作成される予算で、活動レベルが変化しても調整されない。
- ストック・オプション (Stock Option): 特定の期間内に、事前に定められた価格で会社の株式を購入する権利を従業員に付与する報酬。
- 供給曲線 (Supply Curve): 所与の価格で生産者が販売しようとする財の量を示すグラフ。
- ターゲット残余リスク (Target Residual Risk): 企業が戦略的目標を達成するために積極的に受け入れるリスクのレベル。
- 技術的可能性 (Technological Feasibility): ソフトウェア製品の設計が完了し、テストを通過したと判断される時点。
- テンポラル法 (Temporal Method): 外貨建財務諸表項目を機能通貨に換算する際に、貨幣性項目と非貨幣性項目で異なる為替レートを適用する方法。
- 移転価格 (Transfer Price): 関連会社間で財やサービスを取引する際に設定される価格。
- 未割当ファンド残高 (Unassigned Fund Balance): 使途が制限されていない政府会計ファンドの残高。
- 観察不能なインプット (Unobservable Inputs): 公正価値測定において、市場データから導き出せないインプット。
- 変動製造コスト (Variable Manufacturing Costs): 生産量に比例して変動する製造コスト。
- 変動予算 (Flexible Budget): さまざまな活動レベルで費用を調整する予算。
- 変動持分事業体 (Variable Interest Entity, VIE): 議決権以外の理由で支配される可能性のあるエンティティ。
- 分散投資 (Diversification): 投資ポートフォリオのリスクを軽減するために、さまざまな資産に投資すること。
まとめ:BARのリリース問題で学習ポイントを押さえる
BAR受験生が合格するために何をどのように学習すべきなのでしょうか。
BAR科目は、旧BECの主要な計算とCOSO ERMの継続的な重要性に加えて、FARからの再分類によって、高度な会計基準の理解と適用が不可欠となりました。
リリース問題に基づき、BAR学習法についてアドバイスをすると、このようになります。
(1)管理会計と財務管理の計算問題を徹底マスターする
管理会計と財務管理の以下のような計算問題を徹底的にマスターしましょう。
➀差異分析
直接材料費、直接労務費、製造間接費の各差異計算は頻出です。公式を覚え、様々なパターンで計算練習を重ねてください。
➁CVP分析
損益分岐点、目標利益達成に必要な販売量、特別注文の判断など、計算問題が多く出題されます。
固定費と変動費の区別を明確に理解することが重要です。
③資本予算
NPV、IRR、回収期間法などの計算とその解釈、そして相互排他的な投資案件の評価基準(NPVの優位性)を理解してください。
➃財務比率
各種比率の計算方法だけでなく、その比率が示す意味、企業活動や経営判断に与える影響を理解することが重要です。
(2)COSO ERMフレームワークを深く理解する
COSO ERMは概念問題が中心ですが、そのフレームワークの5つの構成要素(Governance & Culture, Strategy & Objective-setting, Performance, Review & Revision, Information, Communication, & Reporting)と、それぞれに紐づく原則を暗記するだけでなく、その実質的な意味と関連性を理解することが不可欠です。
リスク対応戦略(受容、回避、追求、低減、共有) の具体例と概念をしっかりと把握してください。
近年ではESG(環境・社会・ガバナンス)関連のリスクマネジメントへの応用も出題されており、最新の動向にも注意を払う必要があります。
(3)経済学の基礎概念を固める
需要の価格弾力性は頻出です。計算だけでなく、それが収益にどう影響するか、代替品との関連性など、応用的な理解が必要です。
市場均衡、供給曲線・需要曲線のシフトが価格や数量に与える影響をグラフで描いて理解すると良いでしょう。
インフレと実質・名目価値の関係、為替レートの変動とその影響、規模の経済、比較優位といった基本用語とその意味を正確に覚えましょう。
(4)旧FARからの組み換え分野を重点的に学習する
企業結合、ソフトウェア、年金、政府会計といった、旧FARからの組み換え分野を重点的に学習しましょう。
➀企業結合
のれんの計算、測定期間中の会計処理、非支配持分の表示、対価の構成要素、取得日の決定など、複雑な論点が多いです。
➁ソフトウェア開発費
研究開発費として費用化する範囲と資産計上・償却の基準を正確に覚える必要があります。
③年金会計
確定給付型と確定拠出型それぞれの財務諸表の構成、資産・負債の計上方法、費用・収益の認識方法の差異を明確に理解してください。
➃政府会計
ファンド会計の各ファンドの特性と会計基準(発生主義、修正発生主義)、政府全体財務諸表とファンド財務諸表間の調整仕訳、各財務諸表の表示区分など、独特のルールが多いので、丁寧な学習が必要です。特に「管理者による討議と分析(MD&A)」の記載内容も確認しましょう。
(5)日本語解説を最大限に活用する
アビタスで受講生であれば、アビタスが日本語解説を用意してくれていますよね。
正解の理由だけでなく、他の選択肢がなぜ誤りであるかまで詳細に説明されています。
これにより、単に問題を解くだけでなく、関連する概念や応用例まで深く理解することができます。
(6)効率的な学習計画を立てる
BARセクションは範囲が広いため、計画的な学習が不可欠です。苦手分野は早めに特定し、繰り返し演習することで克服してください。
各トピックの概念理解に時間をかけ、その上で計算練習を十分に行うバランスが重要です。
以上、「【BAR】USCPA試験リリース問題(AICPA Released Questions)徹底解説」でした。

重要論点は決まっているんだね。

ぜひ、この傾向に従って、BAR対策を進めて合格してね。
USCPA試験については、どこの著書『USCPA(米国公認会計士)になりたいと思ったら読む本』も参考にしてくださいね。
USCPA短期合格のコツも記載しています。
(2026/01/15 09:33:51時点 Amazon調べ-詳細)
まだUSCPAの勉強を始めていない場合は「USCPAの始めかた」も参考にしてください。